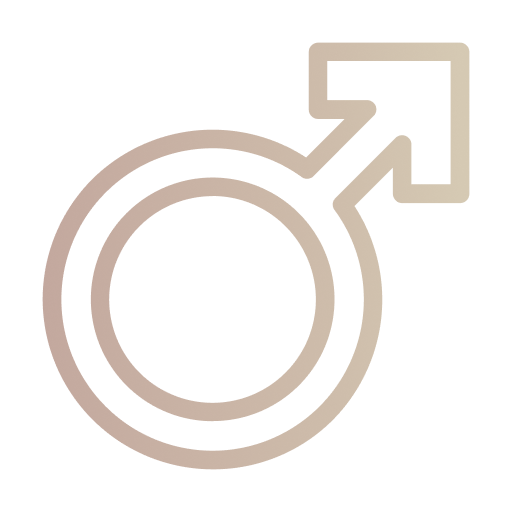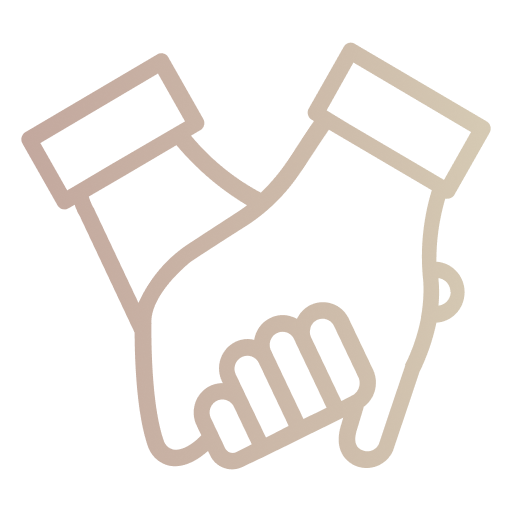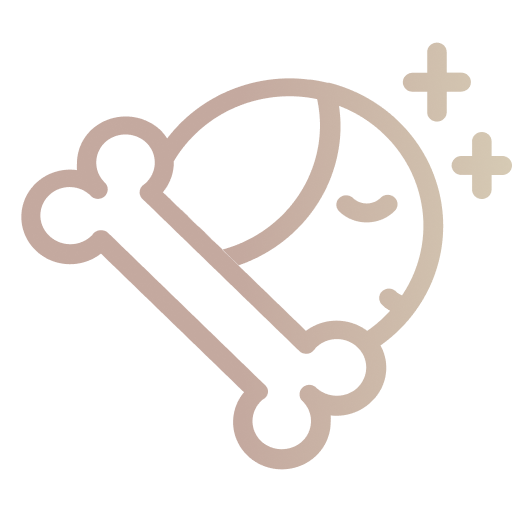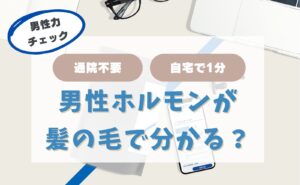内科医が教える! 男性更年期障害の予防対策とストレス解消法

コロナ禍で増加したと言われている症状の一つは、男性ホルモンであるテストステロンの低下によって引き起こされる男性更年期障害(LOH症候群)。ある調査では、40代から50代の男性の10人に1人が経験したとも言われています。
そこで今回TRULYがお話を伺ったのは、内科医の立場から医療に関する情報をわかりやすく解説し、さまざまなメディアで発信を続けているナビタスクリニック理事長の久住英二先生。男性更年期障害の予防対策だけでなく、ストレスのチェック方法や生活改善における注意点などについて教えていただきました。
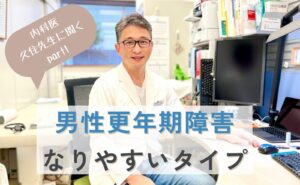
Q.男性更年期障害の発症を遅らせるもしくは、予防するにはどうしたらいいですか?
女性と同じく、男性も発症を遅らせることが大切になってきますので、そのために意識して欲しいのは、「運動をして体を鍛えること」「太り過ぎないように体重を管理すること」「定期的に性生活を行うこと」。それができれば苦労しないと言われてしまいそうですが、つまりアクティブでヘルシーに生きるということですね。
>>男性ホルモンが数値で分かる!誰にも知られずにチェック
Q.運動の目安があれば、教えてください。
どれくらいがベストかというのは、色々と言われていますが、有酸素運動なら1回30分を週3回まで。それ以上すると、ひざや足首などを痛めてしまい、スポーツによる障害が起きる可能性があります。また、筋トレに関しては、1時間のメニューを週1回していた人の寿命が一番長かったというデータが出ているようです。筋トレには抗うつ効果がありますし、体力維持はもちろん、疲れにくい体を作ることができます。
ただ、週に1回だとなかなか筋肉が付きにくいと思うので、筋肉が維持できて多少パンプアップもしたい人には週2回くらいをオススメしています。内容としては、自重トレーニング(腕立て、腹筋、スクワット)で十分ですが、それができないくらい筋力が落ちている場合は、ウエイトトレーニングで軽く負荷をかけながら調整してみてください自重トレーニング含め、フォームやスピードは大切です。ネットでNHK筋肉体操の動画を見ながら行うのを勧めています。
Q.食生活において、心がけたほうがいいことはありますか?
摂って欲しいのは、タンパク質。体重1キロに対して1グラムを1日の目安に摂っていただきたいです。豚肉の赤身だと、だいたい20%がタンパク質。100グラムに20グラム入っていると覚えていただき、朝昼晩にうまくわけて摂っていただけたらいいかなと。あとは腸内細菌を健康的に維持するうえでは、食物繊維もしっかり摂っていただきたいです。
Q.逆に気を付けたほうがいいことがあれば、教えてください。
注意して欲しいのは、炭水化物の摂りすぎとお酒の飲みすぎ。特にお酒に関しては、適量ならいいと昔は言われていましたが、最近では飲めば飲むだけガンになりやすくなるとされているので体のことを考えるならなるべく少なめがいいですね。
ただ、人はお酒を飲むと他者に対して非常に共感的になり、話がうまくできるようになるので、ソーシャルな面においてのメリットはあるのではないかなと。少量でも気分が楽しくなるようなプラスの働きがあると思うので、個人的には週2~3回に1、2杯を飲むくらいなら許容範囲かなと思っています。
Q.ストレスも男性更年期障害を引き起こす要因となりますか?
更年期障害のみならず、ストレスは体にも心にも色々と影響があります。ただ、ストレスというのは、障子の桟(さん)に溜まるホコリのように、知らないうちに積み重なっていくもの。なかなか避けられないものなので、発散するしかありません。そのためには、運動や趣味など、自分が好きなことをして「うれしい」とか「楽しい」といった気持ちになれるように意識してください。
Q.ストレスが溜まっているかどうか、自分でチェックできる方法はありますか?
わかりやすいところだと、眠れなくなっていたら相当ストレスが溜まっている証拠。疲れているなら眠れるはずと思われがちですが、実は疲れすぎると眠れなくなります。なので、もし目覚ましが鳴る前に目が覚めるようになったら気を付けましょう。「パッと目が覚めて爽快!」と思うかもしれませんが、それはつねにテンションが高くなっている状態なので要注意です。
そのほかには、お腹が張る、便秘、胸やけ、目の周りが痙攣する、立ちくらみなどもストレスのサイン。更年期ではないのにのぼせるのも、ストレスによる自律神経の乱れが引き起こす症状の可能性があります。
Q.ほかにも、生活改善で意識したことがいいことがあれば教えてください。
睡眠時間は、7時間が一番いいとされています。4時間以下のショートスリーパーや9時間以上のロングスリーパーもいますが、どちらも寿命が短くなると言われているので、そういう方は改善するようにしてください。
あと、カフェインの摂りすぎもよくないので、飲むのであれば午前中に1、2杯が理想的。睡眠の質が悪くなってしまうので、なるべく午後や夜は飲まない方がいいですね。そもそも、4杯以上飲むとカフェインの目覚まし効果はなくなると言われています。カフェインを摂らないとだるくなるという人は、カフェイン中毒になっているかもしれません。
Q.男性更年期障害に対して不安を抱いている方に向けて、アドバイスをお願いします。
僕は「依存のポートフォリオを作ってください」というお話をよくしますが、ストレスを解消する方法をなるべくたくさん見つけて欲しいと思っています。なぜなら、1つのことだけで発散しようとすると、アルコール中毒や買い物中毒のように何かの中毒になってしまう可能性があるからです。そうならないためにも、トレーニングや食事、山登り、カメラ、音楽みたいな感じで幅広く依存して、ストレス発散することをオススメしています。
あとは、一度は誰かに相談してみること。自分だけで考えていると、間違っていることにも気が付けない場合がありますし、聞いてもらうことで気持ちが楽になることもあります。医療従事者に限らず、パートナーや家族でもいいので、気軽に相談に乗ってくれる人を見つけるようにしましょう。
お話をうかがった先生
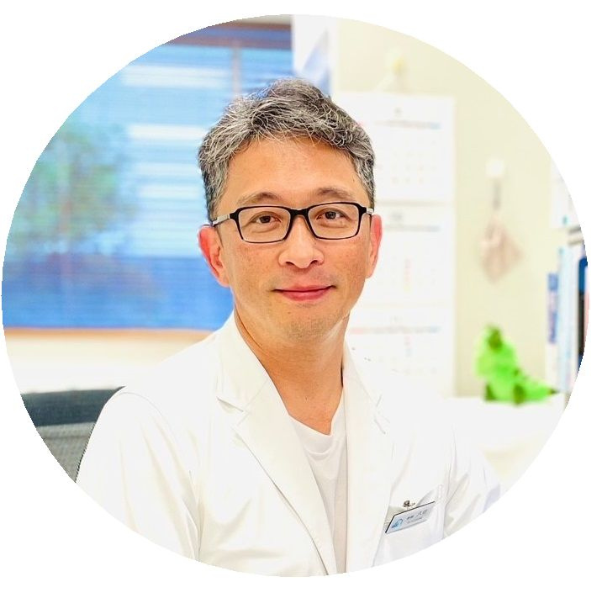
監修医師
久住英二 先生
ナビタスクリニック内科医師。
医療法人社団鉄医会理事長。
1999年新潟大学医学部卒業。
内科医、とくに血液内科と旅行医学が専門。
虎の門病院で初期研修ののち、白血病など血液のがんを治療する専門医を取得。血液の病気をはじめ、感染症やワクチン、海外での病気にも詳しい。
現在は立川・川崎・新宿駅ナカ「ナビタスクリニック」を開設し、日々診療に従事している。