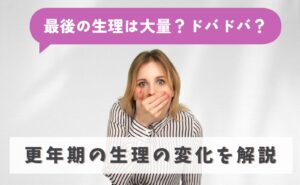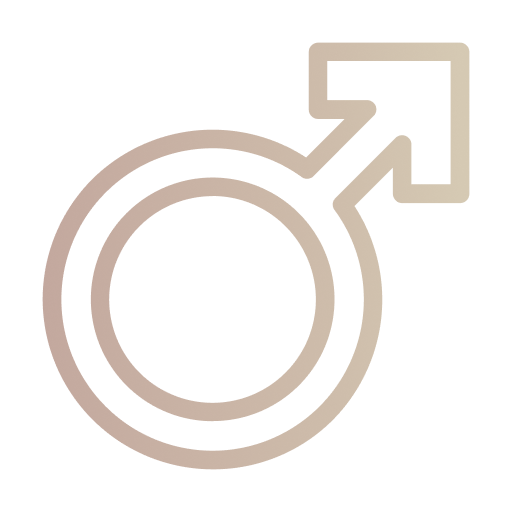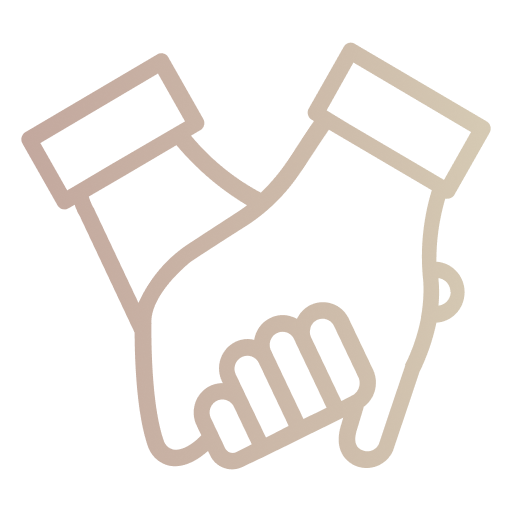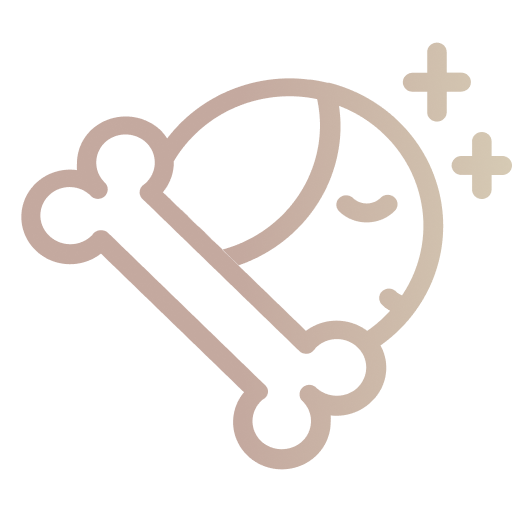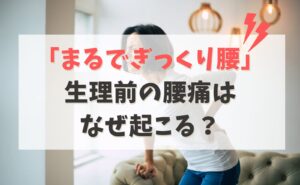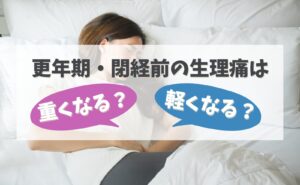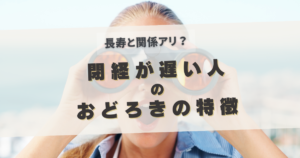【体験談】低用量ピルを子どもに勧める?副作用や親子の対話など気になることは?

今回は、40歳以上の女性を対象に、ピルに関するアンケートを実施。ピルを使用したきっかけや自分の子どもに飲ませているかどうかなどについてのリアルな回答をご紹介したいと思います。
TRULYとライフスタイルストアPLAZAとのコラボレーションで開催された、TRULY世代とZ世代による座談会。その際に話題となったピルに対する認識の違いが、今回のテーマのきっかけに。特に、ピルへのハードルが低くなりつつある若い世代とピルにネガティブなイメージを持っている親世代の間には、さまざまな相違があることが明らかになりました。
ケース1 メリットが上回れば飲ませたい(48歳・女性の場合)
30代後半から40代前半まで、生理痛を軽減させるためにピルを飲んでいたというこちらの女性。自身の子どもに飲ませるかどうかについては、「生理痛がひどいときや生理日をずらしたいときなど、ピルを飲むメリットがデメリットを上回るときには飲ませたい」と話しています。
ピルに関してだけでなく、生理が来たときの対処方法や妊娠の危険についても普段から娘さんと1対1で話し合うこともあるのだとか。子どもに対してオープンな姿勢で接することは、いざというときに相談しやすい環境を作るうえでも欠かせないことだと言えそうです。
子どものピル服用に関して悩みを抱えている方へアドバイス
ピルはそれほど怖い薬ではないので、まずはよく調べてみて、メリットが大きいときには選択肢の一つとして考えればいいのではないでしょうか。自分のお子さんに飲ませるかどうかは、最終的には本人次第ですが、産婦人科の先生に相談してみるといいと思います。
ケース2 家族間で話し合うようにしている(62歳・女性の場合)
こちらの女性がピルを飲み始めたのは、40歳くらいのときで、きっかけはホルモンバランスを整えるためだったといいます。現在は、娘さんもすでにピルを服用しており、肌が荒れを改善させるために飲み始めたそうです。
意識しているのは、ホルモンバランスや更年期、肌荒れ、手足の冷えなどについて家族間で話し合うこと。ピルや生理への対処法に関しては、親の経験値が子どもに影響を及ぼすことが多いとされているので、お互いに正しい知識を身に着けるのは大切なことでもあります。
子どものピル服用に関して悩みを抱えている方へアドバイス
「きちんと容量などを守って飲む分には、そんなに怖い薬ではないですよ」ということは伝えたいですね。
ケース3 副作用が心配…子どもには飲ませたくない(55歳・女性の場合)
「20代のときに生理が止まらなくなってしまい、婦人科でピルを処方してもらいました」と話すこちらの女性。自身が頭痛や吐き気の副作用を経験したこともあり、自分の子どもには飲ませたくないと明かしています。
生理痛や経血量などについて話す機会が増えたのは、娘さんが出産を経験してから。ピルに関しては、治療の一環として飲むことは良いと思っているものの、避妊が目的ならほかの方法を勧めたいと考えているようです。
子どものピル服用に関して悩みを抱えている方へアドバイス
副作用がなく、身体に合うのであれば、良いと思います。いずれにしても、まずは担当医に相談し、納得したうえで服用することを勧めたいです。
今回のアンケートで一番多く見られたのは、「自分の子どもには飲ませたくない」という回答。その理由としては、「身体に負担がありそう」「太りそう」「若いうちから飲むとよくなさそう」といった声が多く上がりました。さまざまな情報が飛び交うなかで、ピルに対して間違った偏見を持ってしまったり、不安に感じたりする方も多いと思うので、まずは婦人科の医師などの専門家からきちんと説明を受け、ピルに対する正しい知識を持つことから始めましょう。
「TRULY」LINE公式アカウント
女医や専門家による正しい情報を配信中!