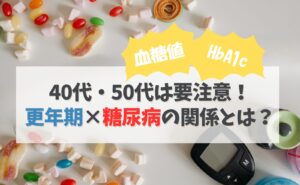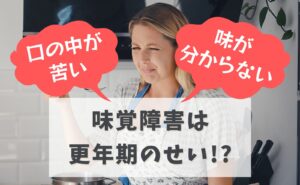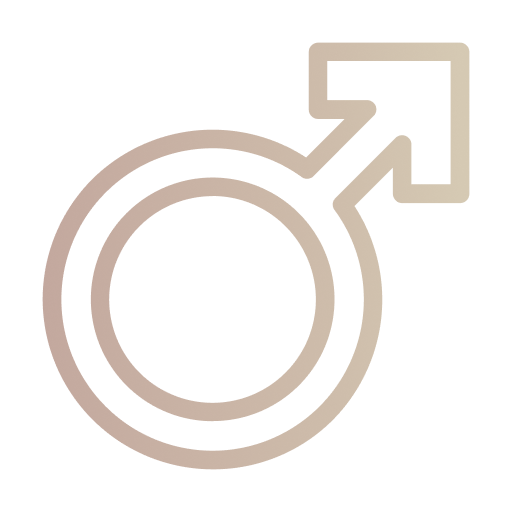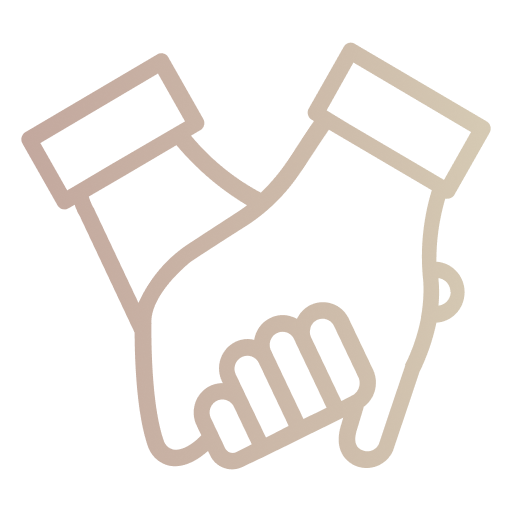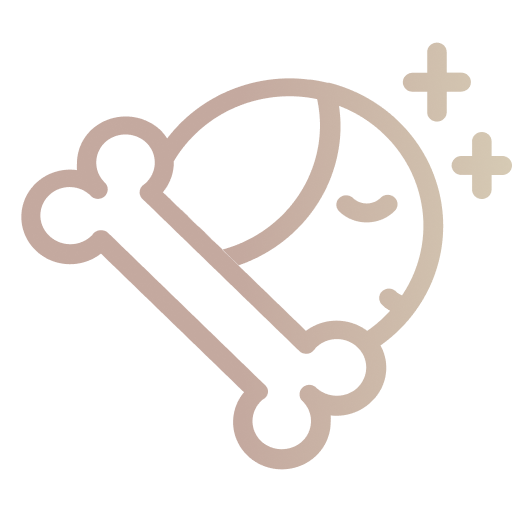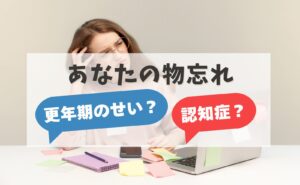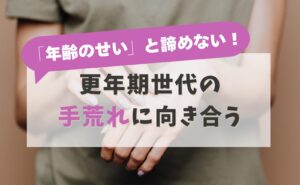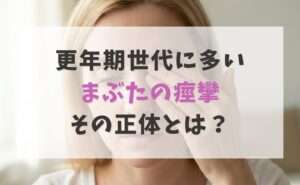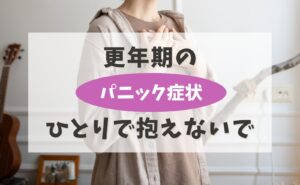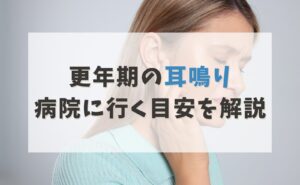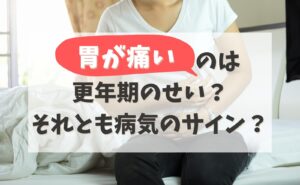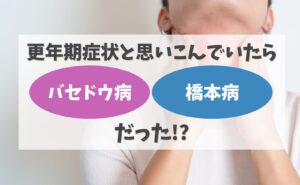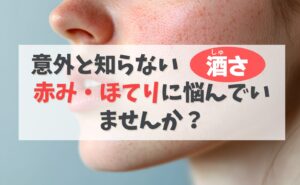更年期は糖尿病になりやすい?血糖値改善対策を紹介
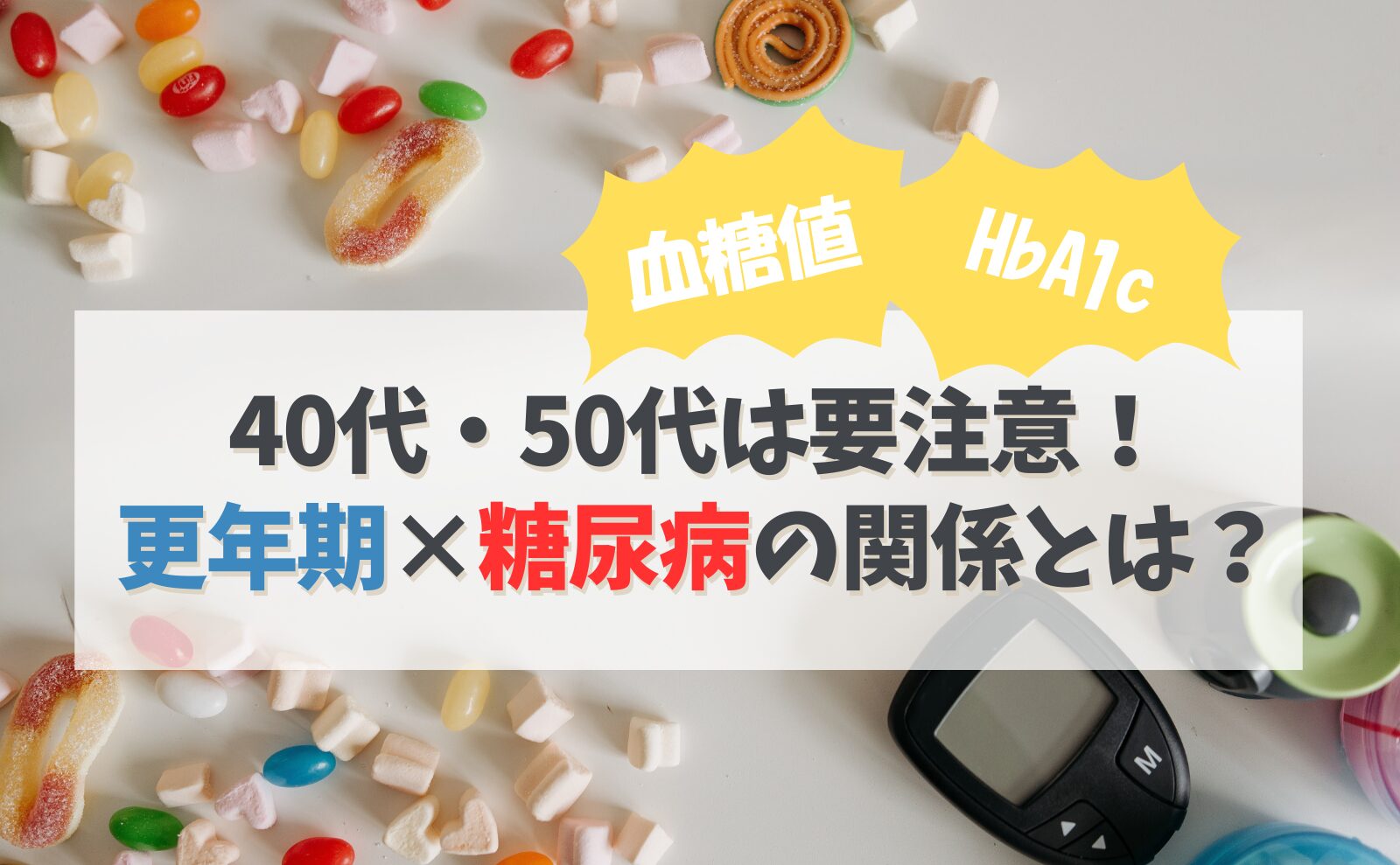
更年期は、女性の体にさまざまな変化が起こる時期です。その中でも見過ごせないのが、血糖値の問題。更年期が「糖尿病のリスク」と密接に関係していることをご存知でしょうか。
この記事では、更年期女性がなぜ糖尿病になりやすいのか、その理由と、血糖値をコントロールするために今日から取り組める実践的な対策をご紹介します。
「血糖値にコレステロールも」健診結果に焦った40代女性の体験談
48歳の栄子さん(仮名)は、会社の健康診断の結果を見て驚きました。
「え!?血糖値にコレステロールも引っかかってる」
これまで健康診断で異常を指摘されたことがなく、健康には自信があった栄子さん。とてもショックを受けてしまいました。
更年期世代に【糖尿病リスク】が高まる理由
40代、50代を迎える女性の皆さん、健康診断の結果にドキッとした経験はありませんか?
実は、この年代の女性は、血糖値やHbA1cの異常を指摘されるケースが少なくありません。背景にあるのは、更年期という女性特有の体の変化。更年期に血糖値が上がりやすい理由は、以下の要因が関係しています。
女性ホルモン「エストロゲン」の減少
更年期は、卵巣機能が徐々に低下し、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が大きく減少する時期です。エストロゲンは、血糖値を下げるインスリンの働きをサポートする重要な役割も担っています。エストロゲンが減少するとインスリンの効果が弱まり、体が糖を上手に利用できなくなり、血糖値が上がりやすくなってしまいます。
体重・内臓脂肪の増加
更年期世代は基礎代謝が低下し、若い頃と同じ食事量でも体重が増加しがちです。特に注意したいのが、お腹周りに脂肪がつく「内臓脂肪型肥満」。内臓脂肪は、インスリンの働きを邪魔する物質を分泌するため、血糖値の上昇に拍車をかけることが知られています。
また、仕事や家庭のストレス、忙しさから食生活や運動習慣が乱れがちになるのも、更年期世代の特徴です。不規則な食生活、運動不足、睡眠不足は、血糖値コントロールをさらに難しくします。
このように、更年期には女性ホルモンの減少に加え、ライフスタイルの変化も重なり、糖尿病発症リスクが高まりやすくなるのです。
40代・50代《血糖値・HbA1c》平均値は?
健康診断の結果を正しく理解するために、40代・50代の血糖値とHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)の平均値と基準値を知っておきましょう。
- 血糖値:検査した時点での血液中の糖の量を表します。その日の体調や食事内容によって変動しやすいのが特徴です。
- HbA1c: 過去1〜2ヶ月間の血糖値の平均的な状態を反映します。血糖値の「長期的な傾向」を知るための指標です。
<40代・50代女性の平均値>(厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査」より)
- 空腹時血糖値(mg/dL)※最後の食事から10時間以上あけ、早朝空腹時の血糖値
40代: 91.9 50代: 93.4
- HbA1c(%)
40代: 5.4 50代: 5.6
空腹時血糖値が126mg/dL以上、HbA1c 6.5%以上で「糖尿病型」と判定され、糖尿病が強く疑われます。放置せず医師の診察を受けましょう。
空腹時血糖値が110~125mg/dL、HbA1c 6.0~6.4%は「境界型」に分類され、将来、糖尿病に進行するリスクが高まります。生活習慣の見直しや、定期的な検査を心がけましょう。
自覚症状がなくても、健診や検査で異常を指摘された場合は、医師に相談することをおすすめします。
糖尿病の初期症状をチェック
糖尿病の初期は自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行してしまうことが少なくありません。以下の症状に心当たりがないかチェックしてみましょう。
□のどが渇く
□頻尿
□倦怠感
□体重減少
□傷の治りが遅い
□手足のしびれ
□目がかすむ
これらの症状が複数当てはまる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
血糖値を下げる!更年期の予防&対策
更年期における血糖値の上昇を防ぐためには、日々の生活習慣を見直すことが何よりも大切です。無理のない範囲から始めて、少しずつ習慣化していきましょう。
食事のポイント
食事量は腹八分目を意識しましょう。余分なカロリー摂取を控えることが、血糖値管理につながります。
野菜、きのこ、海藻類など食物繊維を多く含む食品は、糖の吸収を穏やかにし、腸内環境も整えてくれます。主食は白米だけでなく、玄米や麦ごはん、雑穀パンなど全粒穀物を積極的に取り入れると、食物繊維が補えます。
肉、魚、卵、大豆製品などのタンパク質もバランス良く摂りましょう。
ケーキやジュース、菓子パンなどは、血糖値を急激に上げてしまうため控えめに。
食べる順番にもコツがあります。最初に食物繊維の多い野菜や海藻類、次にタンパク質、最後に炭水化物という順番で食べると、食後の血糖値急上昇を和らげることができます。
よく噛むことで、血糖値を下げるインスリンの初期分泌※が促されます。同時に消化促進や満腹中枢の刺激による食べ過ぎ防止などの効果も期待できます。
※初期分泌とは、食事をしたときに膵臓のβ細胞から最初に分泌されるインスリンのことです。食後、血糖値が上がり始めると、すい臓はすぐにインスリンを分泌し、この「初期分泌」によって血糖値の急上昇を抑えます。
適度な運動
ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、インスリン抵抗性※を改善し、血糖値を下げる効果が期待できます。
※インスリン抵抗性:インスリンが十分に分泌されていても、体がその働きにうまく反応できなくなり、血糖値が下がりにくくなる状態
筋力トレーニングもおすすめです。筋肉量を増やすことで基礎代謝が上がり、糖の代謝も活発になります。毎日30分程度の運動を目標に、無理のない範囲で継続しましょう。
質の良い睡眠
睡眠不足になると食欲増進ホルモン(グレリン)が増え、血糖コントロールが乱れやすくなります。毎日同じ時間に寝起きする、寝る前のカフェインやスマートフォンの使用を控えるなど、規則正しい睡眠習慣を大切にしましょう。
ストレス管理
ストレスは血糖値を上昇させるホルモン(コルチゾールなど)の分泌を促します。趣味やリラックスできる時間を作るなど、自分なりのストレス解消法を見つけましょう。深呼吸や瞑想なども、手軽にできるストレス解消法としておすすめです。
定期的な健康診断
血糖値やHbA1cなどを定期的にチェックし、気になる症状や健診異常があれば、早めに医療機関を受診しましょう。
更年期になったら血糖値の変化に気をつけよう
更年期は、女性ホルモンの減少により、糖尿病リスクが高まりやすい時期であることをお伝えしました。血糖値の上昇を放置すると、目(網膜症)、腎臓(腎症)、神経障害などの「三大合併症」や、心筋梗塞・脳卒中などの重大な病気を引き起こすリスクが高まります。
「今まで大丈夫だったから」と油断せず、バランスの良い食事、適度な運動、質の良い睡眠、ストレス管理を心がけ、健康的な更年期を送りましょう。 少しでも気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。
参考文献
- 厚生労働省. 令和5年国民健康・栄養調査報告. 第2部 身体状況調査の結果. p126-131. https://www.mhlw.go.jp/content/001435374.pdf (閲覧日:2025年5月7日).
- 国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター. 糖尿病とは? https://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/010/010/01.html (閲覧日:2025年5月7日).
- 山内敏正, 門脇孝. インスリン抵抗性のメカニズムと病態生理. 日本内科学会雑誌. 2009;98(4):731-738. https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/98/4/98_731/_pdf (閲覧日:2025年5月7日).
- PubMed. Shukla R, et al. The effect of food order on postprandial glycemic response in healthy subjects. Diabetes Care. 2015 Jul;38(7):e98-9. doi: 10.2337/dc15-0223. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30101510/ (閲覧日:2025年5月7日).
- Schwartz MD, et al. The impact of sleep disorders on glucose metabolism: endocrine and molecular mechanisms. Diabetol Metab Syndr. 2015 Mar 17;7:25. doi: 10.1186/s13098-015-0018-3. https://dmsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13098-015-0018-3 (閲覧日:2025年5月7日).