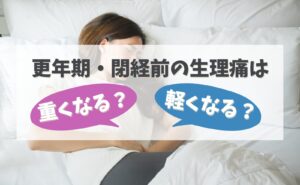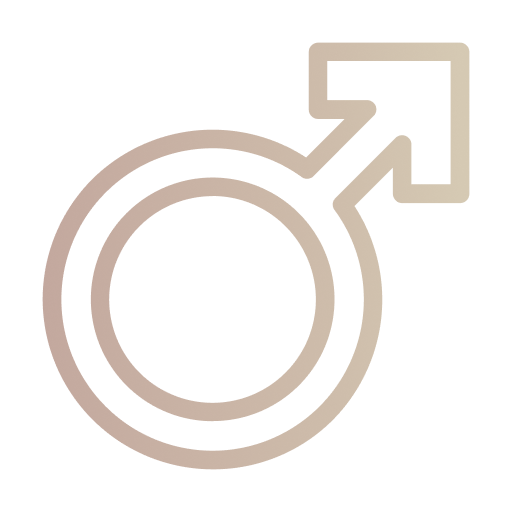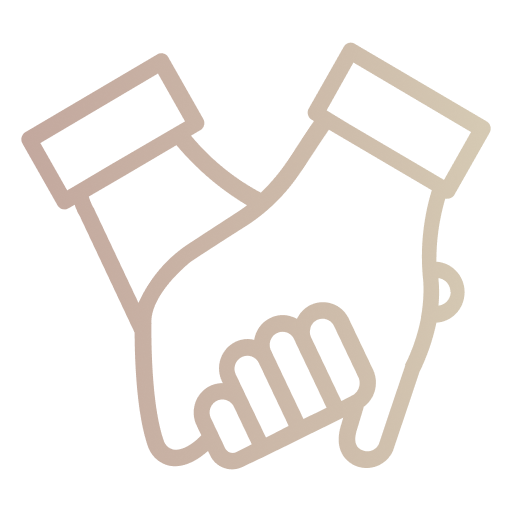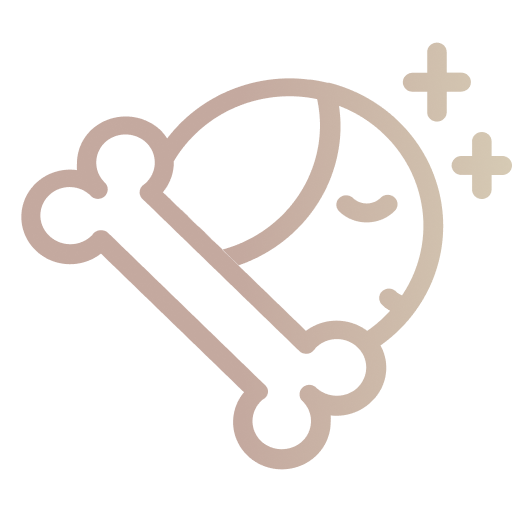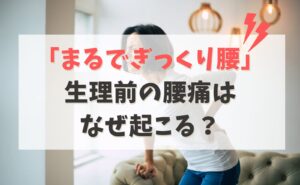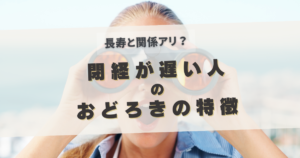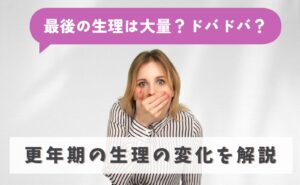《閉経後の子宮筋腫》大きくなる・不正出血が続くのは要注意!
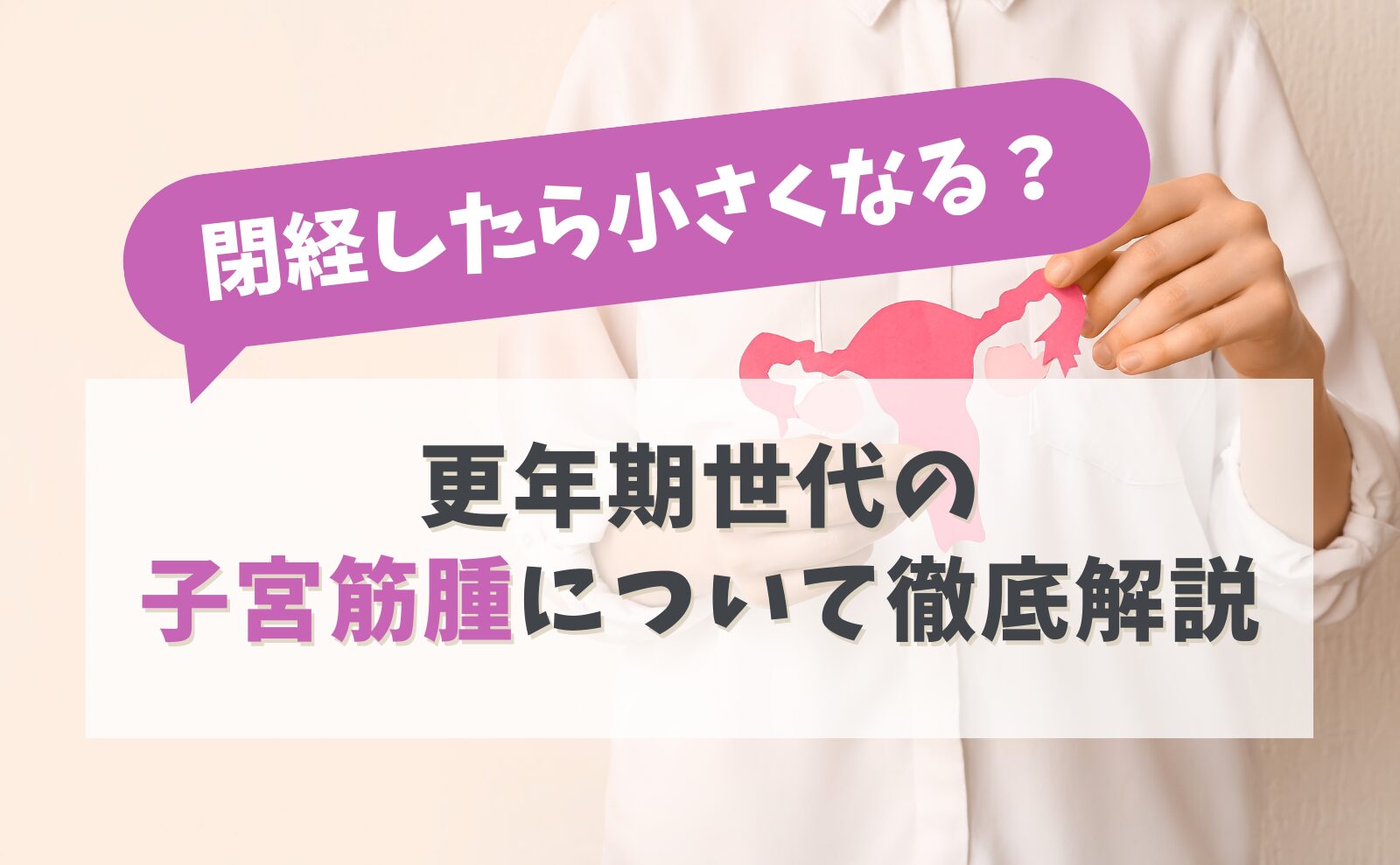
子宮筋腫は、閉経とともに女性ホルモンの分泌が減ることで自然に縮小することが多いといわれています。しかし、閉経後にも不正出血などの症状が続き、婦人科を受診した結果、初めて子宮筋腫と診断されたり、元々あった子宮筋腫が大きくなっていると指摘されるケースも全くないとは言えません。なかには、手術が必要となることも。
この記事では、閉経後の子宮筋腫が引き起こす症状やリスク、適切な対処法を医療情報にもとづき解説します。さらに、不正出血から子宮筋腫が発覚し子宮全摘手術に至った体験談も紹介します。
子宮筋腫とは?閉経後はどうなる?
子宮筋腫は子宮の良性腫瘍で、30歳以上の女性では20〜30%に見られる疾患です。1更年期までは女性ホルモンの影響で大きくなることがありますが、閉経後はホルモンの分泌が減少するため、発育が止まるか縮小する傾向があります。2
子宮筋腫の約95%は子宮体部に発生するとされています。[1]ただし、閉経後にも筋腫が残る場合や、大きくなるケースもあるため注意が必要です。
子宮筋腫<3つのタイプと症状>
子宮筋腫は、発生する部位によって以下3つのタイプに分けられます。[2]
- 筋層内筋腫
- 粘膜下筋腫
- 漿膜下筋腫
それぞれのタイプによって現れる症状や体への影響も異なるため、特徴を理解しておきましょう。
1.筋層内筋腫
子宮の筋肉の層に発生する、もっとも多いタイプで、全体の60〜70%にのぼります。[2]このタイプの子宮筋腫は、ある程度の大きさになるまで自覚症状が出にくい特徴があります。
主な症状は、大量月経や下腹部の圧迫感、頻尿などです。
2.粘膜下筋腫
子宮内膜のすぐ下にでき、子宮の内側に向かって突出する筋腫で、小さくても出血症状が出やすい傾向にあります。月経過多や不正出血、貧血を引き起こすことが多く、不妊症や不育症など妊孕性への影響も指摘されています。3)
3.漿膜下筋腫
子宮の一番外側の膜にでき、子宮の外側に向かって発育するタイプです。[2]子宮の内腔には影響しにくいため月経異常は少ないものの、大きくなると周囲の臓器を圧迫し、頻尿、便秘、腰痛などを引き起こすことがあります。
なぜ閉経後に子宮筋腫が大きくなる?
通常、子宮筋腫は閉経とともに縮小することが多い傾向にあります。しかし、まれに閉経後も増大するケースがあります。3その場合、良性の筋腫ではなく、悪性腫瘍である「子宮肉腫」の可能性も考慮しなければなりません。
子宮肉腫の可能性
子宮肉腫は、子宮筋腫と見た目や初期症状が似ている悪性腫瘍です。4画像検査だけでは判別が難しいこともあり、特に閉経後に筋腫が急速に大きくなったり、不正出血がある場合には注意が必要です。確定診断のためには、手術で摘出し病理検査を行います。
日本産科婦人科学会のガイドラインでも、閉経後に子宮筋腫が増大する場合は、慎重な経過観察または子宮全摘術を検討する必要があるとされています。[3]
子宮筋腫の変性
閉経後の子宮筋腫が、まれに「変性」によって大きくなる場合があります。変性とは、子宮筋腫の組織が壊死や出血などを起こす変化で、それにより、痛みや発熱、不正出血が起こる場合があり、特に閉経後は注意が必要です。
変性が疑われる場合には、MRIや血液検査などで評価を行い、必要に応じて治療を検討します。
実例から学ぶ!子宮筋腫を放置したことで手術になった体験談
若い頃から生理のたびに出血が多かったという40代後半の女性。
閉経後も時折出血がありましたが、「いつものことだから」と気にせず過ごしていました。しかしある日、強い立ちくらみと意識のもうろうとした状態に襲われ、自ら救急車を呼ぶ事態に。
病院で検査を受けたところ「粘膜下筋腫」が見つかり、出血の原因であることが判明しました。医師からは、今後も出血を繰り返す可能性が高く、貧血が悪化する恐れがあると説明され、子宮全摘術を選択しました。
女性は「もっと早く相談していれば、ここまで悪化しなかったのに」「自分の体のサインを無視しなければよかった」と悔しそうに語っています。
子宮筋腫の検査と治療
子宮筋腫が疑われる場合には、適切な診断を受けることが重要です。婦人科では問診をはじめとした各種検査が行われ、筋腫の有無や大きさ、性状、他の疾患との鑑別などが判断されます。
ここでは、診断に用いられる主な検査方法と治療法について紹介します。
婦人科で行われる検査
婦人科で行われる検査として、以下のようなものが挙げられます。[1]
- 問診
- 内診
- 経腟エコー
- MRI
- 子宮鏡検査
- 血液検査
- 子宮内膜細胞診・組織診
まず最初に行われるのは、症状や既往歴を確認するための問診です。そのうえで、内診によって子宮の大きさや形、筋腫の有無を触診します。経腟エコー(超音波検査)では、子宮内の筋腫の位置や大きさを把握します。
さらに、詳細な評価にはMRI検査が用いられ、筋腫の性状や卵巣腫瘍との鑑別、悪性所見の有無を確認します。粘膜下筋腫が疑われる場合には、子宮鏡検査が有効とされます。また、子宮肉腫などを疑う場合には、血液検査により血性LDHの上昇が見られることがあります。
不正出血がある場合には、子宮体がんを除外するために子宮内膜細胞診や組織診を実施するのが一般的です。
更年期女性の子宮筋腫の治療方針
更年期以降の女性で子宮筋腫が見つかった場合、症状がなければ経過観察が基本とされます。[2]閉経後は女性ホルモンの分泌が減少するため、筋腫が自然に縮小する可能性が高いためです。
一方で、出血や貧血、圧迫症状などがある場合は治療の対象となります。治療方法には、薬物療法と手術療法があります。薬物療法では筋腫を一時的に小さくするホルモン療法がありますが、閉経後は、すでに女性ホルモンの分泌量が低下しているためあまり選択されません。
手術療法としては、子宮全摘術が再発予防や根治目的で選ばれやすく、特に閉経後の方に多く実施されます。子宮を残したいという希望がある場合には、筋腫摘出術(筋腫のみの切除)を選択することも可能です。[2]
更年期世代の女性の子宮筋腫は、年齢や閉経のタイミング、筋腫の状態によって治療方針がさまざまであるため、医師とよく相談してみてください。
閉経後の子宮筋腫や不正出血、月経異常は放置しない
子宮筋腫は必ずしも閉経後に縮小するとは限りません。不正出血や月経異常がある場合には、「年齢のせい」「更年期だから」と思わずに、早めに婦人科を受診することが大切です。もともと子宮筋腫を指摘されていた人は、定期的な検診を忘れないようにしましょう。
自身の体調に関心を持ち、気になる症状があれば早めに相談することで、将来的な安心につながります。
参考
「TRULY」LINE公式アカウント
女医や専門家による正しい情報を配信中!