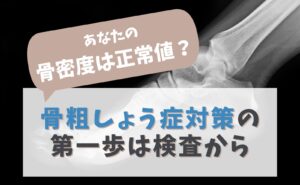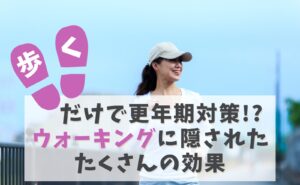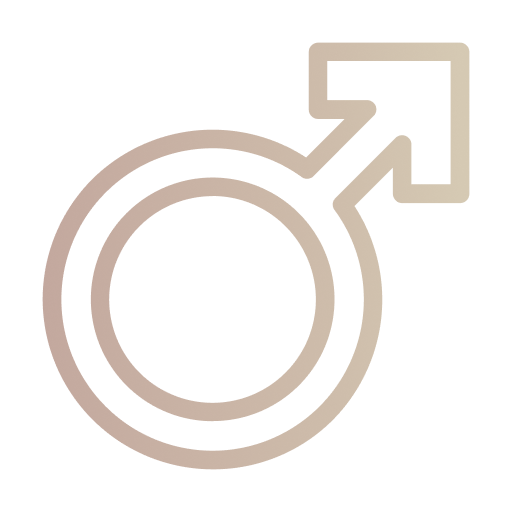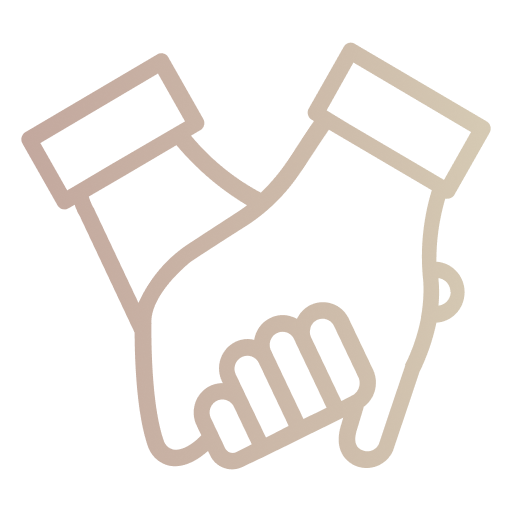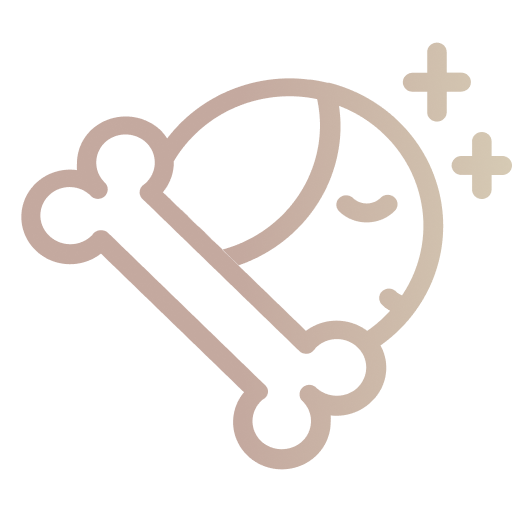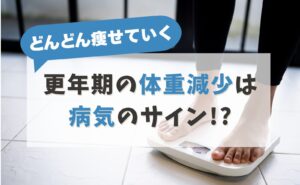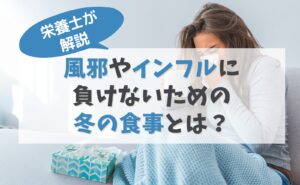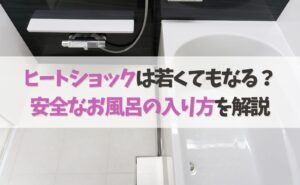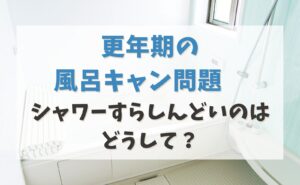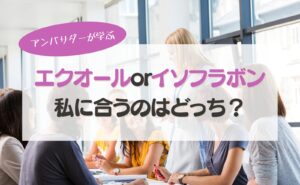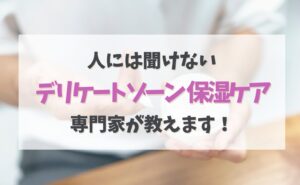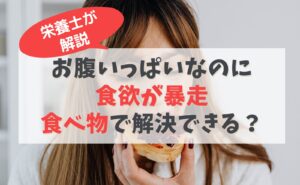50代女性の骨密度の平均は?数値の見方や検査方法を解説
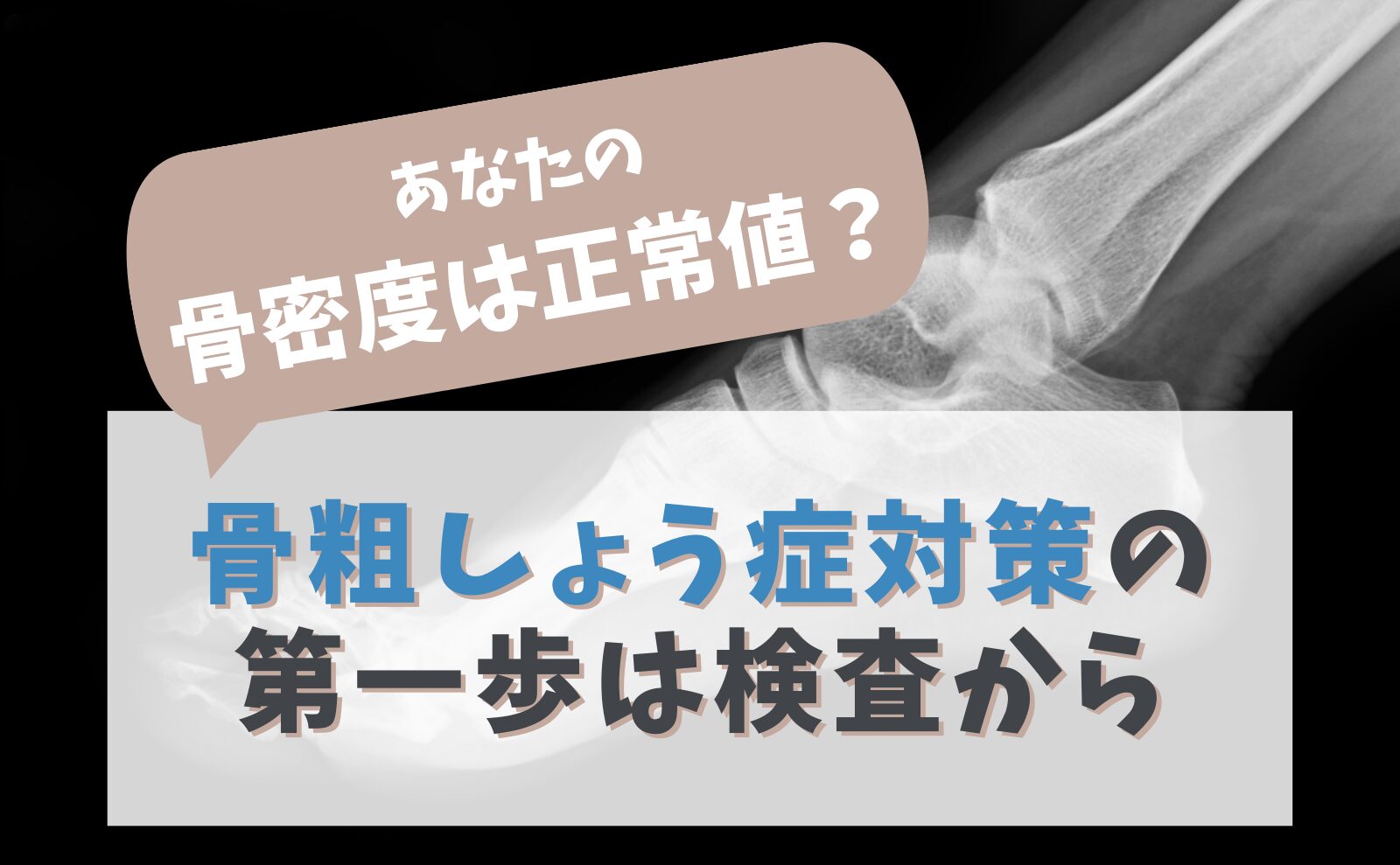
女性は50代になると、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少し、骨密度が低下しやすくなります。骨密度が低下してもすぐに症状が現れるわけではなく、気づかないうちに骨折リスクが高まることもあるため、早めの対策が必要です。
この記事では、50代女性の骨密度の平均値や測定方法、骨粗鬆症のリスクを防ぐための生活習慣や対策について詳しく解説します。今からできる対策を知り、健康な骨を維持していきましょう。
何となく受けた「骨密度検査」の結果
50代の真子さん(仮名)は、会社の健康診断で「骨密度測定」がオプションにあるのを見つけ、なんとなく気になって受けてみることにしました。これまで骨の健康なんて特に意識したことはなかったけれど、更年期世代だし、ちょっと気をつけた方がいいのかもという軽い気持ちだったそうです。
数日後、届いた結果には「やや低下」との記載。すぐに深刻な問題ではないようだけど、見慣れない言葉に思わず手が止まりました。
「やや低下って、どういう意味?平均より低いってこと?それってもう骨粗しょう症ってこと?」
今すぐ何かしなくてはいけないのか、将来骨折しやすくなるのか……初めて直面する“骨の不安”に、戸惑いを抱えているようです。
50代女性が骨密度を知ることの重要性
50代女性は閉経に伴い、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が急激に減少します。エストロゲンは骨の新陳代謝を促進し、骨密度を維持する役割を担っていますが、その分泌が低下すると、骨の強度が低下しやすくなります。12345
骨密度の低下は自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに骨折リスクが高まるため、早めの対策が重要です。[1][2]
特に50代は、骨の健康を守る分岐点となる時期だといえます。骨密度を測定し、食事や運動、生活習慣を見直し、将来的な骨粗しょう症のリスクを抑える必要があるのです。[5]
骨密度とは?骨粗しょう症との関係は?
骨密度は、骨の強さを示す指標の1つであり、骨に含まれるミネラル(カルシウムやリンなど)の量を測定することで評価されます。
骨密度の低下が進むと骨の強度が弱まり、骨粗しょう症のリスクが高まります。骨粗しょう症になると骨がスカスカになってもろくなるため、転倒やくしゃみなど、わずかな衝撃で骨折することも珍しくありません。1)
50代女性の骨密度【正常値・注意すべき数値】
骨密度は、骨の健康状態を数値で示す指標です。
一般的に「YAM(Young Adult Mean)」という指標を用い、若年成人(0〜44歳の健康な成人)の平均値と比較して何%あるかで評価されます。この数値によって、骨の強さや骨粗しょう症のリスクが判断されます。[1]
YAM90%以上は正常範囲、80〜90%が骨量減少気味のライン、80%未満では詳しい検査が必要、70%未満になると骨粗しょう症と診断されます。現在の骨密度を把握し、適切な対策を講じることが大切です。[1][4]6
| 数値 | 判定 | 対策 |
| YAMの90% | 異常なし | ・骨量減少を食い止める生活をする |
| YAMの80〜90% | 要指導 | ・やや低下・生活習慣の改善を意識する・これ以上骨量が減らないように、食生活を見直し、日常生活に運動を取り入れる |
| YAMの80%未満 | 要精検 | ・詳しい検査が必要・早めに医療機関を受診する・骨粗しょう症と診断された場合には、治療開始 |
参照元:公益財団法人骨粗鬆症財団
特に閉経後の50代女性は骨密度が低下しやすいため、早めの検査と適切な対策が重要です。
検査結果や年齢によってその後の検査の頻度が異なるため、次回の骨密度検査のタイミングについても医師に確認してみましょう。
自分の状態に合わせて定期的な骨密度測定を受け、骨密度の変化を早めに察知し、必要な対策を講じましょう。
骨密度の検査方法
骨密度は自分で測ることはできず、医療機関で専用の機器を用いた測定が必要になります。
骨密度を測定する方法には以下3つの種類があり、それぞれ測定する部位や精度が異なります。
- DXA法
- MD法
- QUS法
最も正確な検査を受けたい場合はDXA法がおすすめですが、手軽に測定したい場合はMD法やQUS法も有効です。ただし、骨密度が低いと診断された場合は、より精密な検査を受けることを検討しましょう。どの検査も1〜8分と短時間で測定でき、痛みを伴うことはありません。
次に、詳しい検査方法を見ていきましょう。
DXA(デキサ)法
DXA(デキサ)法は、最も精度が高く、骨粗しょう症の診断基準にも用いられる骨密度測定法です。高低2種類のX線を測定部位に照射して、その透過度をコンピュータで解析し、骨量を測定します。[1]7
| 測定部位 | ・腰椎(背骨)・大腿骨近位部(足のつけ根)・前腕骨(肘から先) |
| メリット | ・短い時間で済む・誤差が少ない |
| 特徴 | ・放射線の被曝が少なく、体への影響が少ない |
MD(エムディー)法
MD(エムディー)法は、手のひらのX線写真を撮影し、骨密度を測定する方法です。人さし指の骨とアルミニウムの濃度を比較することで、骨の密度を評価します。[1][7]
| 測定部位 | ・(手掌)手のひら |
| メリット | ・簡単に測定でき、クリニックでも実施しやすい |
| 特徴 | ・DXA法に比べると精度はやや低いが、スクリーニングには有効 |
QUS(キューユーエス)法
QUS(キューエス)法は、X線を使用せず、超音波でかかとの骨密度を測定する方法です。骨折リスクを予測するのに役立ちますが、骨粗しょう症の診断や治療効果の判定には使用できません。[1][7]
| 測定部位 | ・(踵部)かかと |
| メリット | ・放射線による被ばくがないため、安全性が高い |
| 特徴 | ・健診などで広く利用され、妊娠中でも測定可能 |
骨粗しょう症になるとどうなる?
骨粗しょう症は、骨密度が大幅に低下し、骨がもろくなることで骨折しやすくなる病気です。
自覚症状がほとんどなく、加齢とともに進行し、気付かないうちに骨折することも少なくありません。症状として、背中が曲がってきた、腰が痛い、身長が縮んできた、などの変化が現れることがあります。[2][6]
特に、転倒による骨折が起こりやすい点には注意が必要です。大腿骨頸部骨折や脊椎圧迫骨折が発生すると、歩行困難や寝たきりにつながるおそれが高まります。生活の質を大きく左右するだけに、早めの予防と対策が大切です。
要注意!骨密度が低下しやすい人の特徴
骨密度の低下は加齢とともに進みますが、生活習慣や体質によってそのリスクが高まることがあります。骨密度が低下しやすい人の特徴を、以下に挙げました。[2][6]
- 乳製品や大豆製品をほとんど摂らない:カルシウム不足で骨がもろくなりやすい
- 運動不足で筋力が低下している:骨への刺激が減り、骨密度が低下しやすい
- 喫煙や過度な飲酒の習慣がある:骨の代謝が乱れ、骨の強度が低下する
- 極端なダイエット経験がある:栄養不足で骨の成長や修復が不十分になる
- 早発閉経(45歳未満で閉経):エストロゲンの減少により骨密度が低下しやすい
- 家族に骨粗しょう症の人がいる:遺伝的な要因で骨密度が低くなる可能性がある
これらのリスクがある場合は、食生活や運動習慣を見直し、骨密度を維持する対策を早めに行うことが大切です。
骨密度の低下を防いで健康的な50代を過ごそう
50代女性は骨密度が急激に低下しやすい時期のため、意識的な対策が必要です。骨の健康を維持するためには、定期的に骨密度の測定を行い、食事・運動・生活習慣を見直すことが重要になります。
また、骨粗しょう症のリスクは骨密度だけでは診断できません。骨の質やその他の要因も関係するため、自己判断せず適切な検査を受けることが大切です。気になる症状がある場合やリスクが高いと感じる場合は、早めに医療機関を受診し、専門家のアドバイスを受けましょう。
参照元