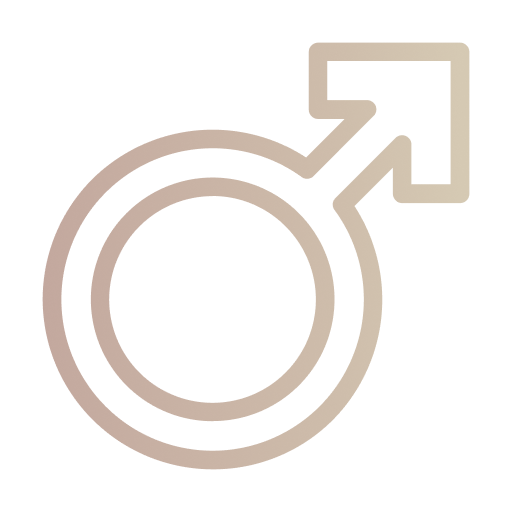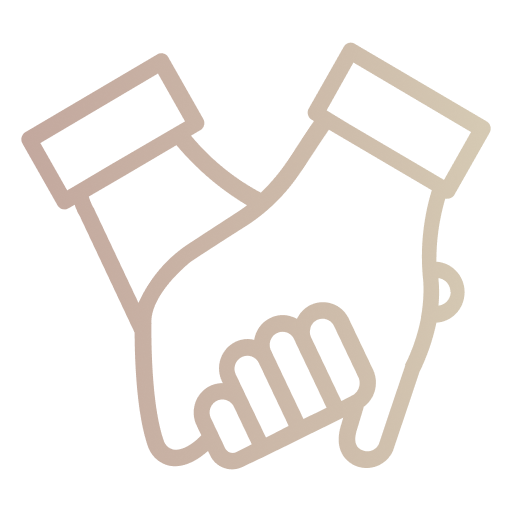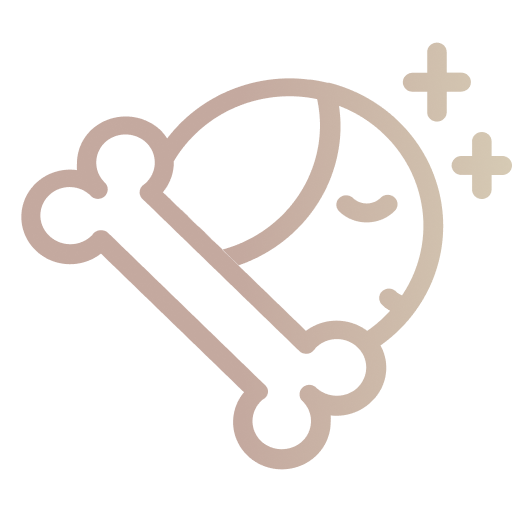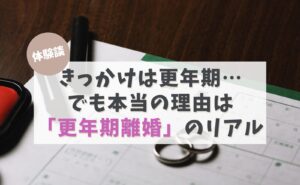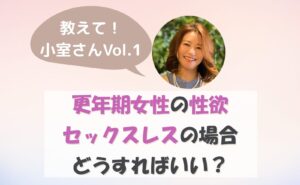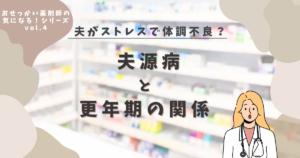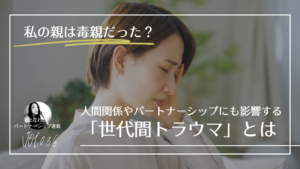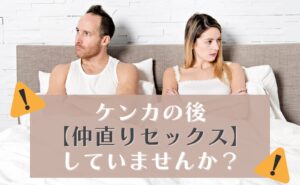コミュニケーションの性差を知る。男性と対等で楽しい関係を築くための「10の愛情表現」<女性編>

こんにちは。セックス・エデュケーターでジャーナリストの此花わかです。
「彼と話が通じない」「何でいちいち説明しないと分からないのだろう」と男性パートナーに対して感じたことがある女性は多いはず。
人間の脳、心や行動は決して性別で一般化をしてはいけません。
しかし社会・文化が決める「男らしさ」「女らしさ」のジェンダー規範は私たちに無意識にすり込まれていることから、コミュニケーションのスタイルにも性差が生まれていると多くのセクソロジストは考えています。
愛情表現というと、スキンシップや、「好きだよ」などの言葉だけだと捉えがちですが、実はコミュニケーションには様々なカタチがあります。
パートナーを理解し、より親密で対等な絆を結ぶには、コミュニケーションの性差を知り、理解することが助けになります。
今回は、コミュニケーションの性差と男性パートナーとリレーションシップを育む「10の愛情表現」を紹介しましょう。
コミュニケーションは言葉だけじゃない
コミュニケーションには4種の非言語と3種の言語コミュニケーションがあり、様々な研究から、私たちがとる日常のコミュニケーションの多くが非言語タイプからきているものとされています。
<4種類の非言語コミュニケーション>
①顔の表情
②ボディ・ランゲージ
③手話
④沈黙
<3種類の言語コミュニケーション>
①聴覚
②言葉・文章・記号
③音楽
「ロマンチックなことを言ってくれない」「愛情を態度で示してくれない」という女性の不満をよく聞きますが、ひょっとしたら彼の非言語的な愛情表現を見過ごしているときもあるかもしれません。
それでは、11冊もの著書があるアメリカの有名なセクソロジスト、アヴァ・カデル博士が説く”コミュニケーションの性差”を見てみましょう。
コミュニケーションにおける12の性差

これらはあくまで”傾向”であり、性別をこえた”個人差”があることを心に留めておき、これらの傾向で個人をジャッジしないようにしてください。(※1)
① 女性は育み、男性は征服しようとする傾向がある
② 女性は理解されて感謝されることを好み、男性は人に影響を与え称賛されるのを好む
③ 女性はリレーションシップを重視し、男性は達成感を重視する
④ 女性は多角的で広い視野で物事を見る一方、男性は狭い視野で物事を観るが、無関係な情報を切り離すことができる
⑤ 女性は感情、リレーションシップと情報を紐付けて考える傾向がある、男性はそれらをすべて切り離して考える傾向がある
⑥ 女性は集中をマルチタスクに分散することが得意だが、男性は長時間、ひとつのタスクに集中することのほうが得意だ
⑦ 女性は複数の課題を同時に考え、男性は課題をひとつずつ分けて考えがちだ
⑧ 男性がもつテストステロンは女性の20倍だから、男性はより自立心が強く支配的な傾向がある
⑨ 女性は匂い、音、タッチ、味などビジュアル以外の感覚を楽しむ一方、男性の第一感覚はビジュアルである(だからポルノをみる男性は多い)
⑩ 女性は相手の全体像や、カップルの性的コミュニケーションに性的妄想を抱き、妄想中の”感情”も重要視するが、男性は相手の”体のパーツ”やオーガズムに性的妄想を抱く
⑪ 男性も女性も生々しい性的な言葉を楽しめるが、女性は”ロマンチックな言葉”にも興奮する
⑫「種の保存」本能により、男性のほうが女性よりも複数恋愛したい傾向がある(ただし、本能と行動は別なので、「男性のほうが女性よりも浮気する」と決めつけてはいけない)
アヴァ・カデル博士は、コミュニケーションの性差を認識・理解した上で、“違い”を尊重し、決してパートナーを100%自分流に変えようとしてはいけない、と言います。
コミュニケーションにギャップがある場合は、違いを尊重しながらお互いのニーズを満足させるための、ギブアンドテイクの交渉が必要。
そもそも、男性と女性はお互いに”外国語”を話しているのだと捉えたほうが気が楽かもしれませんね。
男性とのリレーションシップを育む「10の愛情表現」

まず、女性と男性のコミュニケーションは目的に大きな違いがあります。
女性は”感情”を、男性は”情報”を共有するためにコミュニケーションをとる傾向があります。男性が日常で使う言葉の数は女性の半分ほどだと言われているほど。
例えば、女性同士なら用事がなくても友達にLINEしたりますが、男性同士はそういうことをあまりしません。
そういったコミュニケーションの性差を踏まえて、カデル博士は30年以上ものセラピスト経験から男性に対する「10の愛情表現」を作り出しました。(※1)
① 彼にひとりの時間をあげる
② 彼の趣味に自分のできる範囲で興味をもつ
③ 彼の目の前で、他人に彼を褒める
④ 彼の母親には優しくする(彼の母に失礼な態度を取られていたら断固立ち向かうべきですが)
⑤「あなたといると安心」と伝える
⑥ 家事、育児、日常の雑事を公平に分担する。彼に遠慮せずに色々なことを相談にのってもらう
⑦ 突然、彼に自分のセクシーなセルフィーを送る
⑧ 外出先では、彼を”初めて会った魅力的な男性”のように扱い、恋の戯れを仕掛ける
⑨ 彼にとって重要なことに熱中しているときは、そばにいてもそっとしておいてあげる
⑩ たまに自分からセックスへ誘う
ポイントはダイレクトなコミュニケーションをとること。遠回しに男性の意図を推測するのではなく、簡潔にダイレクトに質問するのがオススメ。
会話の文脈を読むことが苦手な男性は多いので、先に”結論”から話すと意思が伝わりやすいでしょう。
対等で楽しいリレーションシップを育むためには……
忘れられがちなのは「沈黙」もコミュニケーションだということ。世界的な人気を誇るセックス/リレーションシップ・セラピストで、世界的ベストセラーの「セックスレスは罪ですか?」の著者であるエステル・ペレル博士は、「(パートナーへの)欲望は”謎めいていない”と起こらない」と説明します。(※2)
これは、お互いに”馴れ合う”ことなく、”謎めいた”存在でいる、ということ。カップルにとって、日常の全てを分かち合うのが最高のコミュニケーションだとよく言われますが、恋愛のトキメキを維持するためには、実はそうではないのかもしれません。
彼の家族、時間や趣味を大切にしてあげるのと同時に、育児や家事は彼ときちんと分担し、頼れるときは頼る。そうすると、彼は自分の”自由”が尊重されたことに感謝し、パートナーの役に立っていることに達成感を感じ、関係がますます深まるのではないでしょうか?
カップルがお互いの”自分軸”を尊重しながら、絶妙な距離感を保ち恋人関係を作る……慌ただしい日常生活におけるパートナーの存在意義は、そういった対等で楽しいリレーションシップを育むことではないでしょうか。
【参考】
※1. NeuroLoveology: The Power to Mindful Love & Sex」by アヴァ・カデル博士
※2.’Desire Needs Mystery’: 75 Best Esther Perel Quotes on Love and Relationships – Parade