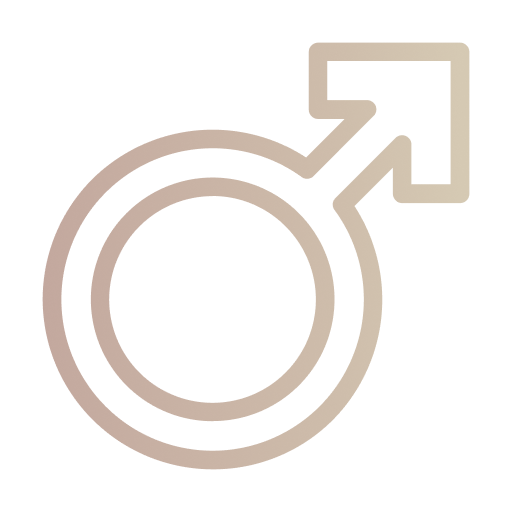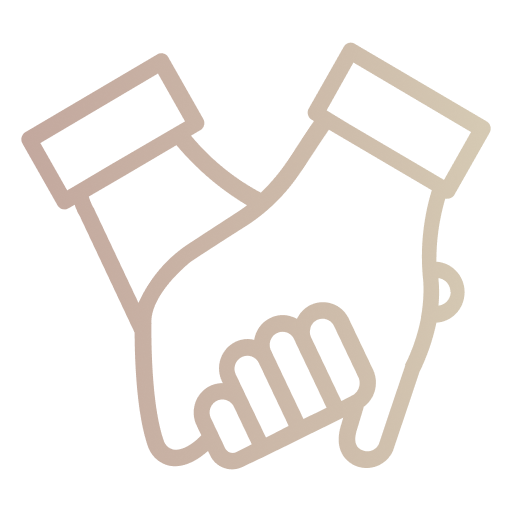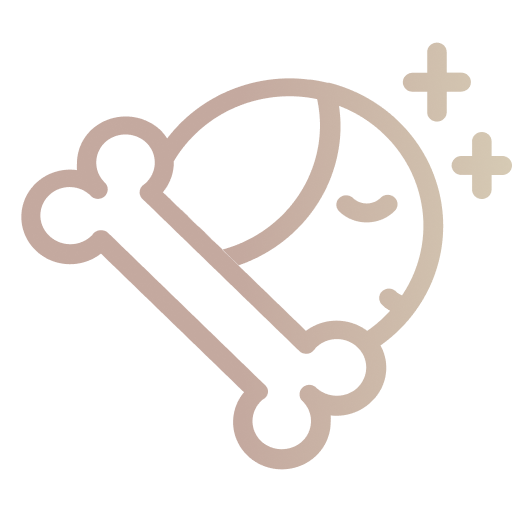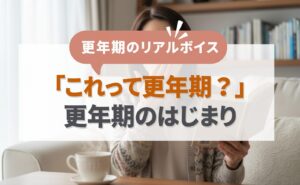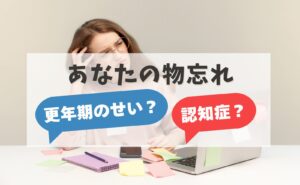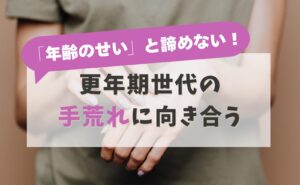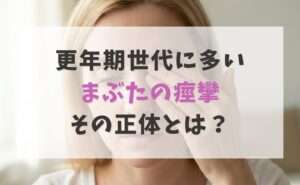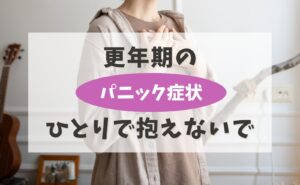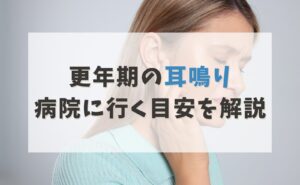これは驚き!更年期の「ホットフラッシュ」で氷を食べるのは間違い?

~今回の体験談は、更年期のホットフラッシュによる汗に対して、アイスを食べて体を冷やそうとする女性の話。ホットフラッシュの対策や注意点をお伝えします~
湯船にはつからず、氷(アイス)を食べるのは間違い?
「今回は90日分のお薬が処方されていますが、服用している方が調子いいですか?」
前回と同じ漢方薬を受け取りに来られた患者様にかけた言葉です。
その患者様は今回で3回目の来局でした。以下その患者様と私のやりとりです。
「最近シャワーだけにしたので、ホットフラッシュはマシになりました。汗が出るのは身体が熱いからでしょう?温まるのは良くないと思い、湯船につかっていません。それに寝汗がひどいから、毎晩アイスを食べて体を冷やしてから寝ています。」
「今晩からゆっくり湯船につかって、アイスを食べるのはやめるようにしてください。更年期はコレステロール値が上昇しやすくなります。かえって血管に悪影響を及ぼします。」
「え?だって汗が出るのは熱いからじゃないのですか?」
うだるような暑い日が続くと自然と汗が湧き出てきます。その影響で、「汗=暑い=身体を冷やす」と考える方が多く見受けられます。
しかし更年期症状に見られるホットフラッシュは、身体が熱いからではありません。
ホットフラッシュの汗の原因は?

ホットフラッシュによる汗は、自律神経がうまく働かず、血管が縮んだり開いたりする調整ができなくなるために起こります。
更年期の不快な症状は、エストロゲンの分泌量が減少するために起こりますが、これらは子宮、卵巣、乳房以外にも、脳、皮膚、粘膜、血管、腸壁、筋肉、関節、骨など様々な場所に影響を及ぼします。
一般的にほてり、紅潮および寝汗は血管運動症状と言われます。血管運動症状は、ホルモンの変化によって発生する温度機能障害の一種です。
体の内部の安定した体温を「中核温」といい、概ね一日の周期で変化します。中核温は、脳や心臓などの大切な臓器の働きを保つために高く安定しています。しかし、ホルモンの乱れにより熱が下がった時の反応が乱れてしまい、血管運動症状を引き起こすと言わています。
自律神経と女性ホルモンの関係
それでは次に、自律神経と女性ホルモンの関係を見ていきましょう。
卵巣機能の低下によって引き起こされる脳の混乱が、自律神経を乱れさせる
女性ホルモンは、卵巣から分泌されていますが、その卵巣に指令を出しているのは、脳の視床下部と下垂体です。
視床下部には、自律神経(血管、血圧、心拍、皮膚、発汗、体温などの血管運動神経)をコントロールする働きがあります。
更年期になると卵巣の機能が低下し、分泌されるホルモンが減少してきます。しかし脳は「もっと出せ」と指令を出し続けます。いくら指令をだしても、卵巣からホルモンが分泌されないため、脳は混乱してしまうのです。
このような状態を繰り返すうちに、ホルモンのバランスや自律神経が乱れてしまいます。そのため、ほてりやのぼせ、めまい、動悸、息切れなど全身の不快な症状や、イライラ、不安などの精神的な症状がでてきます。
暑いからではなく、ほてりを冷ますための発汗
ほてりにより暑いと感じると、視床下部が「今私は暖かすぎる」と誤って感知し、体を冷やすように指令を出します。その結果、皮膚の表面近くの血管は拡張し始め、体温を放散しようとして表面への血流を増加させます。
これにより、肌の色が薄い女性の顔や首が赤く紅潮します。汗をかいて体を冷やす場合もあり、これがホットフラッシュによる汗となります。
その時、心臓の鼓動が速くなったり、心拍数の増加を感じることがあります。ほてりに続いて、しばしば寒気を感じます。
汗は暑いから出ているわけではなかったのです。ホットフラッシュによる体の放熱反応で、末梢血管が拡張し、皮膚の温度が上昇しているだけです。
ホットフラッシュがおこりやすい時期
ホットフラッシュは閉経前から閉経後早期にピークを迎える方が多いと言われています。
期間は人によって異なりますが、2年以内に自然に軽快する人が多く、まれに10年以上持続する場合もあります。
また頻度もばらつきが多く、日本人女性ではおよそ40~70%経験すると言われています。※1 さらに、BMIが高い人は発症頻度や重症度が高いと言われています。※2
ホットフラッシュは1~5分間(通常3分以内)持続する熱感を自覚し、血圧変動はないまま脈拍が7~15拍増加します。通常上半身を中心に、顔面から始まり、頭部、胸部、全身に広がることもあります。発汗を伴うことも多く、夜間に出現すると寝汗となります。
《BMIとは》
Body Mass Indexの略で、カラダの大きさを表す指数です。
BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 理想的なBMI値は「22」とされています。
※1: 日本産科婦人科学会 日本産科婦人科學會雜誌 49(7), 433-439, 1997-07-01参照
※2:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27272227/PMID:27272227参照
ホットフラッシュが起こりやすい原因

ホットフラッシュが起こりやすい原因として、下記の内容があげられます。
生活習慣
- 早期の閉経
- 運動不足
- 肥満
- 喫煙
その他
- 不安障害
- 片頭痛
- 服用薬の影響
ホットフラッシュによって緊張や不安な状態、抑うつが続き不眠がちになり、集中力の低下や倦怠感など次々と症状が現れることがあります。
またアルコール・カフェイン・スパイシーな食べ物は、ホットフラッシュを招きやすいと言われています。
ホットフラッシュの治療方法
ホットフラッシュの治療方法は主にこちらの2つになります。
- HRT
- 大豆イソフラボンなどの補完代替医療
※女性医学ガイドブック参照
※https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24323914/ PMID:24323914
今回ご紹介した女性が服用している漢方薬も、更年期の症状改善目的として治療に使用されています。
日本人女性は海外に比べて比較的ホットフラッシュの頻度が低いと言われています。
アフリカ系アメリカ人の女性はほてりの持続時間が最も長く、約半数が10年以上ほてりを経験しています。ヒスパニック系の女性が2番目に長く、白人、中国人、日本人の女性がそれに続くと言われています。
※PMID: 25686030
【最後に】気を付けてほしいこと
のぼせ、ほてりには、他の病気が隠れていることもあります。
「ホットフラッシュだからいつかおさまる」と容易に自己判断をしないでください。
血圧や甲状腺に異常がある可能性も考えられます。たとえば、動悸、息切れ、頭重、手足のしびれなどがある場合は、「高血圧」の可能性があります。
高血圧とは、上が140mmHg以上、下が90mmHg以上です。閉経以降、エストロゲンの減少によって血圧が高くなりやすくなります。
高血圧は、脳卒中や心臓病などのリスクが高まります。今まで低血圧だった人も要注意です。私の患者様で、朝の血圧は低くても、仕事中、ストレスにより200mmHg近くになる方がおられました。
また、ホットフラッシュの症状に、イライラ、発汗、脈が早くなる、体重減少などがある場合は、「甲状腺機能亢進症」の可能性も考えられます。甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンの分泌が過剰になる病気です。
そして、最後はいつも同じ話になってしまいますが、生活に支障をきたす症状が出ている時は、まずは専門医を受診してくださいね。