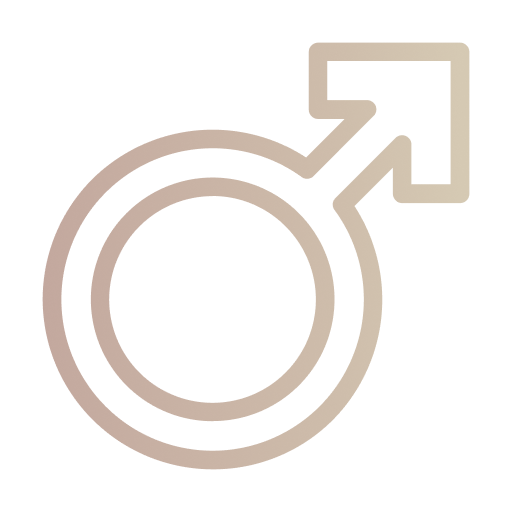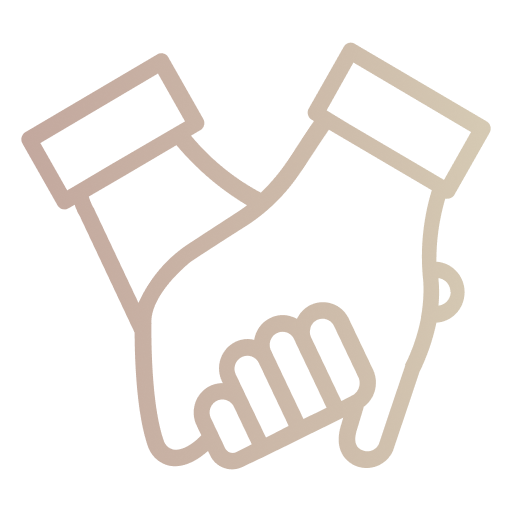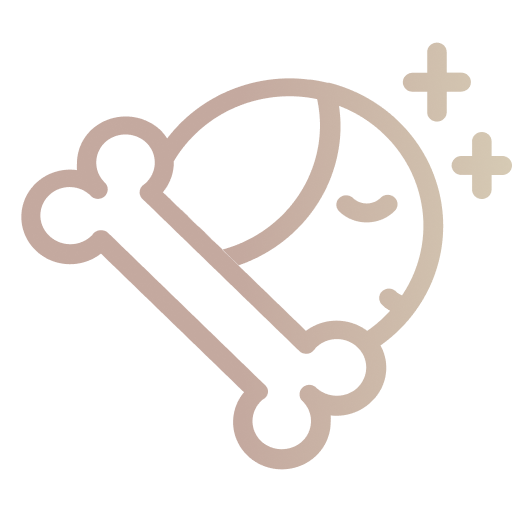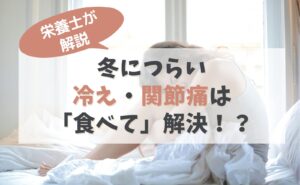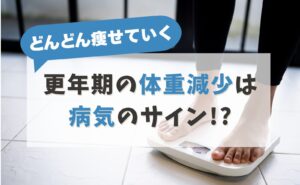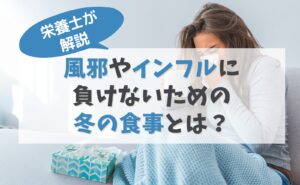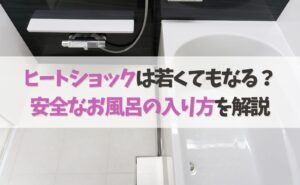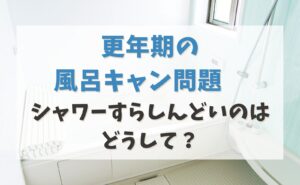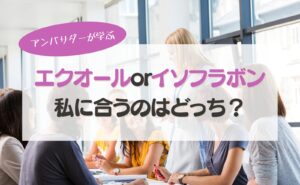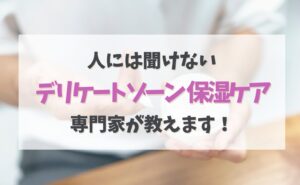【体験談】男性更年期障害どうする?パートナーの女性にアドバイス

自分が更年期で悩んでいるとき、大きな支えとなるのがパートナーの存在。特に、症状がつらいときに気遣ってくれると、それだけで心が軽くなるのを感じる人も多いのではないでしょうか?
とはいえ、男性にも更年期障害は起こります。男性の更年期障害は、男性ホルモンであるテストステロンの低下によって引き起こされるものです。テストステロンは40代から徐々に減少しますが、生活習慣やストレスなどが原因で急に減少することもあります。そのため40~60代と、幅広い年代で起こる可能性があります。もしかしたらパートナーも同じような症状に悩まされているかもしれません。
そこでTRULYでは、40歳以上の女性のなかから「パートナーが男性更年期を経験した人」を対象にアンケートを行いました。今回は、男性更年期になったパートナーの症状や対処法などについて、女性たちの声をご紹介したいと思います。
>>本当に男性ホルモン減ってるの?簡単にできる検査方法
ケース1 「ストレス発散方法を考えてあげる」(男性44歳 女性43歳)
「主人が40歳くらいのときに、少しのことで怒り出すようになり、すぐにイライラするようになりました」と語るこちらの女性。話すのも嫌になるときもあったそうですが、症状が出たあとは、お灸でストレスを発散してもらったり、男性ホルモンを整える漢方を飲んでもらったりして対処したと言います。そのほかに意識していたのは、仕事に関して「今日はどうだった?」と話しかけることや相手が食べたい料理を作ってあげることだったそうです。
男性更年期になっているパートナーを持つ女性にアドバイス
あまりに旦那さんがイライラするようになり、いつもよりも頻繁に起きているかなと思ったら、まずは話を聞いてあげましょう。それで気分が治らないようなら、温泉などでストレスを発散してもらうのがオススメです。それでもダメなら、やはり一度病院に行ったほうがいいかもしれません。
ケース2 「いままでと変わらない対応をしてあげる」(男性48歳 女性43歳)
「病院で診察してもらったわけではありませんが、3年くらい前から主人が更年期のような症状です」と話す女性。その理由としては、些細なことでイライラしたり、暑くもないのに汗をダラダラとかいたりしていたから、だと言います。とはいえ、病院に行くように勧めても、認めたくないのか全く行ってくれないのだとか。気にされることを嫌がるため、なるべくいままでと変わらず、普通の生活をするように意識しているのだそう。
男性更年期になっているパートナーを持つ女性にアドバイス
旦那さんがイライラしていると、こちらもついイライラしてしまうかもしれませんが、そんなときは「これは更年期だから仕方ない」と思って割り切った方がいいと思います。
ケース3 「ケンカにならないように生活時間をずらす」(男性57歳 女性54歳)
こちらの女性の場合は、パートナーの方が44~47歳の頃に、更年期障害に陥ってしまったと話します。具体的な症状としては、睡眠障害。眠れなくなったことで、徐々に顔の印象まで変わってしまったため、心療内科に行って、睡眠導入剤を飲んでいたのだそう。「男性更年期ですという診断はいただけませんでしたが、いま思うとあれがそうだったんじゃないかなと主人とも話しています」と振り返ります。当時は、旦那さんがちゃんと眠れるように、ベッドに入ったあとは、大きな音を立てないようにつねに気を遣って生活をしていたのだとか。旦那さんも、そのことにはとても感謝を示してくれたと言います。
男性更年期になっているパートナーを持つ女性にアドバイス
こちらもイライラする年齢なので、お互いがギスギスしてしまいがちです。私たちの場合は、睡眠が問題だったため、別々に生活するくらいの時間のペースにしたところ、ぶつかり合うこともなく過ごせました。症状にもよるので、一概には言えませんが、いつまでも続かないので、がんばってください!
ケース4 「体に良さそうな食事を作ってあげる」(男性49歳 女性45歳)
「最初の症状は、42歳のときにEDになったことです」と打ち明けるこちらの女性。その後は、慢性的な疲労やイライラすることが増え、男性更年期を疑ったのだとか。対処法としては、疲れやすさには疲労が取れる食事を用意し、EDには亜鉛やマカの補給、イライラは放置するようにしていたそうです。
男性更年期になっているパートナーを持つ女性にアドバイス
やっぱりおいしいご飯を作ってあげると喜んでくれるので、ぜひ体に良さそうな食事を提供するようにしてあげてください。
以上、パートナーが男性更年期を経験している女性たちの声をお届けしました。男性のなかには、いまだに「男性には更年期はない」と思い込んでいる男性もいるため、病院に行きたがらないという声が多くみられました。
まずは、客観的に見て、男性更年期の可能性があるかを確認すること。そして、相手のことを否定するようなことを言わずに、じっくりと話を聞いてあげることが大切です。そのうえで、症状がひどくなる前に、病院へ行くようにうまく誘導してあげましょう。更年期というつらい時期を一緒に乗り越えれば、さらに絆を深められるはずです。
この記事を監修した専門家

監修助産師/看護師
東衣里
助産師として大学病院産科病棟・外来にて勤務。その後、大手百貨店で妊娠・出産・育児を中心とした相談業務を担当。また、都内複数の区からの委託を受け、こんにちは赤ちゃん訪問(出産後の新生児訪問)にも従事。
現在はTRULYにて、チャット相談業務や記事執筆などを担当。地方へ移住して、リモートワークという形で仕事とプライベートを両立。自身も、働く女性・一児の母として、困っている女性の気持ちに寄り添った、実現可能なアドバイスを心がけている。