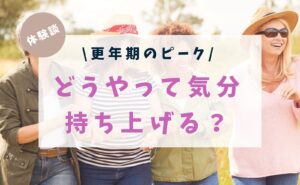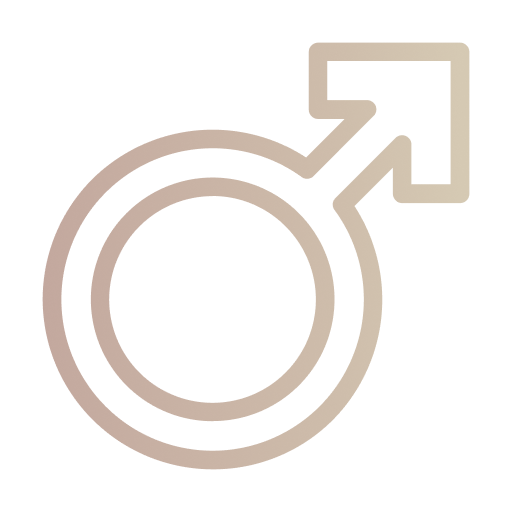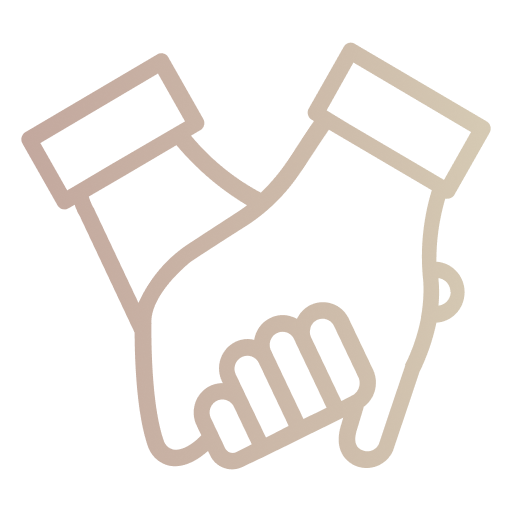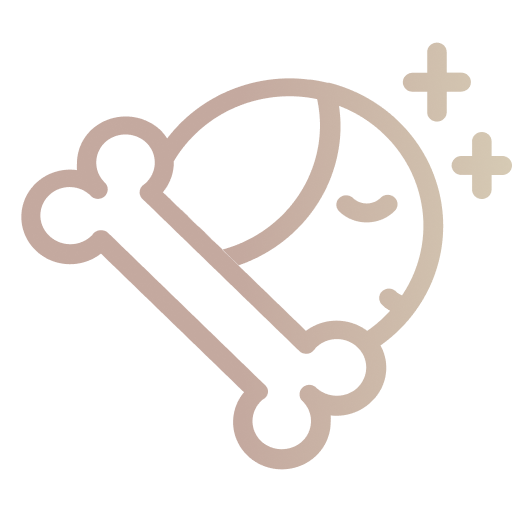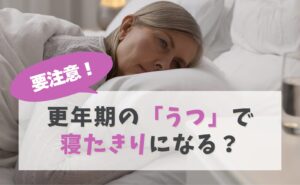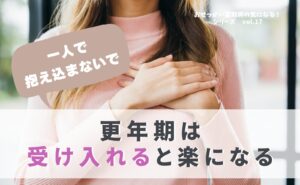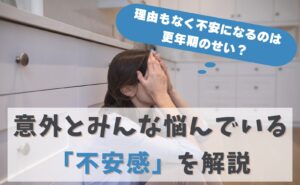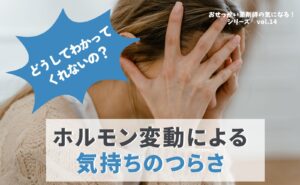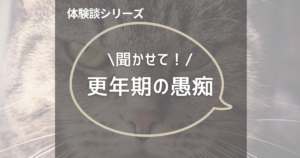女性医師に聞く、産後うつと更年期うつ。病院に行く適切なタイミングとは?

充実した日常生活を送るうえで、いまや欠かせないもののひとつと言えば、メンタルヘルスのケア。ひと昔前に比べて、「産後うつ」や「更年期うつ」といった言葉をよく耳にするようになっている現代だからこそ、女性が抱えるうつに対する関心が高まっています。
特に、女性ホルモンのバランスが乱れやすい更年期に差し掛かっている人にとっては、うまく乗り切るためにも基礎知識を身に着けたいところですよね。そこで今回は、家庭医療専門医として女性の健康に向き合い続けている三島千明先生に、女性とうつの関係性や病院を受診する際の心得などについて教えていただきました。


Q.女性がうつ病を発症しやすい時期というのはありますか?
一般的に女性のほうが男性よりもうつ病にかかりやすいことが分かっています。なかでも、発症しやすいのは、産後や更年期といった女性ホルモンの影響を受ける時期。そのほかにも出産や育児、仕事や家事の負担、夫やパートナーとの関係、親の介護や子どもの巣立ちといったさまざまなライフイベントによる変化をたくさん抱えていることも要因とされています。誰もがそういったことをひとつずつ乗り越えてはいますが、いくつもの出来事が同時に重なると、それが大きなストレスとなり、うつのリスクが高まってしまいます。
Q.主な症状はどのようなものでしょうか?
ゆううつになったり、やる気が出なかったり、気分が落ち込んでいる状態のことをうつ状態といいます。更年期の女性は半数近い方がうつ状態を経験すると言われているほど。実は、それくらいうつは女性にとって身近な症状なんです。みなさんも、これまでにそのような状態を一度は味わったことがあるのではないかと思います。ただし、それがずっと続いて、仕事が手につかなかったり、生活が立ち行かなくなったりしたときには、治療が必要です。実際、うつ病という病気には厳密な診断基準があり、いろいろな条件を満たした状態が2週間以上続いたときに、初めて診断されています。
うつ病は精神的な症状だけではありません。眠れなかったり、食事が食べられなかったりといった体の不調を最初に認識することもあります。そのほかにも疲労感や倦怠感、胸がドキドキしたり、息苦しくなったりさまざまな不調としてあらわれることがあります。
Q.ちなみに、産後と更年期では、うつの症状も異なりますか?
まず産後に関しては、ほとんどの女性が“マタニティブルーズ”と呼ばれる気持ちの落ち込みや浮き沈みを感じます。普通は1~2週間ほどで自然とよくなっていくものですが、それが深刻な形で続いてしまい、眠れなかったり、頻繁に泣いたり、気分の変動が激しかったりすると産後うつが疑われます。約1割の方が経験していると言われています。
更年期うつは、まず発症する年齢や時期が異なります。また、気分が落ち込むといううつ部分は似ていますが、自律神経の乱れによって引き起こされる身体の不調が一緒に起こることがあるので、産後うつよりもさまざまな身体の症状のパターンがあると言えます。「顔や身体がほてる」「めまい」「汗をかきやすくなる」「夜寝付けない」「物忘れが多い」などが挙げられますが、人によっても表れ方はさまざまです。
Q.どのタイミングで診察を受けるのが適切なのでしょうか?
実際には、生活に支障が出てとても困っている段階になってから診察に来られる方が大半なのですが、医師としてはもう少し早く来ていただきたいというのが本音です。うつと言っても、先ほどのように、女性ホルモンやストレスが影響している場合もあれば、もともとその方が持っている素因による場合など要因は多岐に渡っています。うつだと思っていても身体の異常による原因が隠れていることもあります。でも、早めに来ていただければ、診察や必要な検査をして、現状の評価をし、治療やきちんとしたセルフケアの指導をすることができます。対処が早ければ早いほど改善は早くなる可能性は高いです。
働く女性のなかでも、特に真面目な性格の方は休むことに罪悪感を抱いてがんばりすぎてしまう方が多いのですが、辛い症状を我慢することはよくありません。仕事に行けなくなってしまうほどになってからではなく、落ち込む日がいつもより続いたり、睡眠や食欲が普段と違うと感じたりするような兆候があった段階で診察を受けたほうがいいと思います。
Q.その場合、何科に行けばいいのか悩む方も多いと思うのですが、どのようにすればよいですか?
最初は内科や婦人科でもいいので、まずは身近なかかりつけの医師に相談してみてください。例えば、健康診断や風邪等で以前かかったことがあるところで、話しやすいなと思うところがよいかなと思います。というのも、普段の自分を知っている医師のほうが、患者に注意が必要かどうかの判断がしやすいからです。
また、いきなり精神科や心療内科に行くのは少しハードルが高いと感じている人もいらっしゃるかと思います。実際、初めて会った医師に自分のことを話すのはパワーのいることですし、医師も患者のことを理解するのに少し時間がかかってしまうものなので、そういう観点からも、定期的に通っているところのほうが、何かあったときに相談がしやすいですよね。
ちなみに、いまは専門外のことは医師同士が連携するのが一般的です。最初に診察した後に、より専門の医師に相談したほうがいいと判断すれば、適切な別の医療機関を紹介します。そういった意味でも、普段からいろいろな話ができるかかりつけのお医者さんを持つことをオススメしたいです。
Q.精神科と心療内科の違いについても教えていただけますか?
まず精神科というのは、名前の通り精神的な病気を専門に扱っているので、気分の落ち込みや不安が強い場合、幻覚や幻聴のような精神的な症状がある場合に受診が適切です。それに対して心療内科は、心が関係する内科。つまり、心理的なストレスや心の問題が原因となって体に症状が表れる場合に適している科のことです。主な症状としては、「動悸がする」「頭が痛い」「喉がつかえる」「眠れない」といったものが挙げられます。
非常にわかりづらいところではありますが、この2つの専門性は重なる部分がありますので、基本的にうつの相談ならどちらに行っても問題はありません。診察をするなかで、医師が必要と感じたら、別の科に行ったほうがいいかを助言する場合もあるので、いずれにしてもまずは早めに相談してみるのがいいかなと思います。
Q.では、カウンセラーの役割についても、ご説明いただけますか?
カウンセラーとは、心理的な問題を解決するカウンセリングのプロのこと。多くは臨床心理士や専門の資格を持っています。医療では精神科や心療内科の医師と連携して心や対人関係などの悩みを抱えた人を支援します。医師は、うつの治療について薬の治療や環境調整だけではなく、カウンセリングをお勧めする場合があります。通常の診察よりもゆっくりと時間をかけて、しっかりと話を聞いてくれるというのが、カウンセリングの特徴。理解や共感をしながらその方の問題点を明らかにしてくれるので、最近では治療に組み込むケースが増えています。心理カウンセラーは医療以外にも学校や企業の中で活躍しています。最近はオンラインカウンセリングのサービスもあり、気軽に利用しやすくなってきています。
Q.自分に合った病院や医師を探す方法があれば、教えてください。
確かに、クリニックの評判をネットで探しても本当かどうかわからないので難しいところですよね。医師と患者の相性も人それぞれです。だからこそ、ここで価値を発揮するのが先ほどからお話しているかかりつけ医の存在。なぜなら、普段から信頼している医師が紹介してくれるところなら安心して行くことができますし、それによって話しやすくなるというのも大事なことだからです。繰り返しにはなりますが、まずは気軽に話せる医療従事者や相談窓口を見つけて欲しいなと思います。
お話をうかがった先生

監修医師
三島千明 先生
島根大学医学部を卒業したのち、島根大学医学部付属病院で初期臨床研修を修了。
その後、北海道家庭医療学センターで、家庭医療後期研修を修了する。
現在は、青葉アーバンクリニックや丸の内の森レディースクリニックにて勤務。女性医師として、悩みを抱える女性たちが気軽に相談できるようなかかりつけ医を目指し、診療を心がけている。専門分野は、総合診療(家庭医療)、在宅医療。