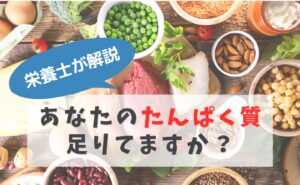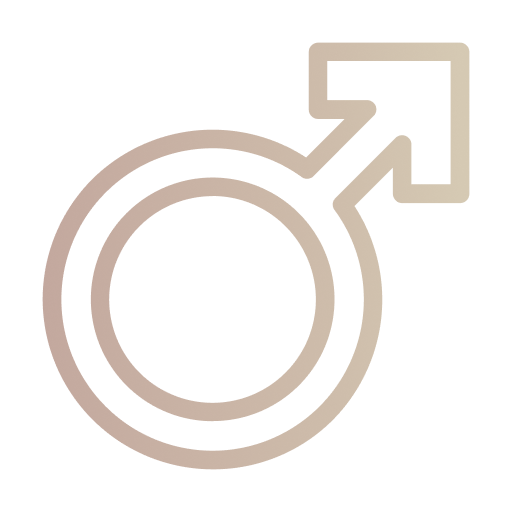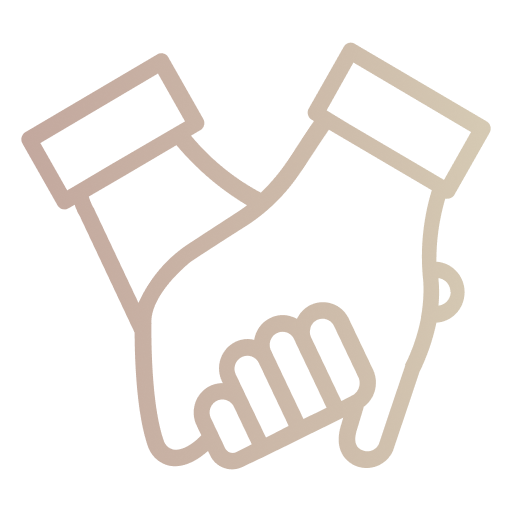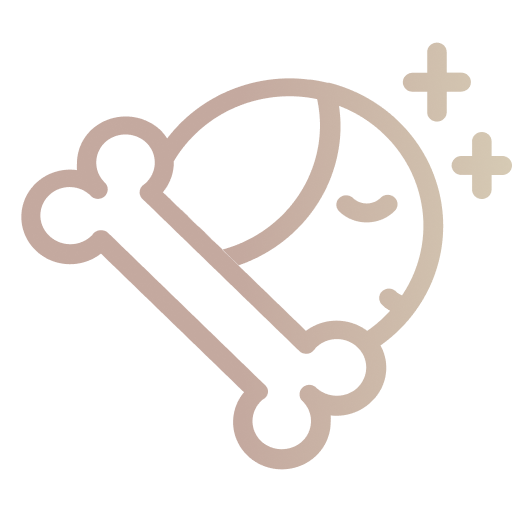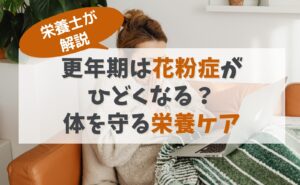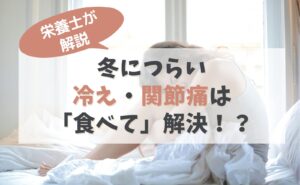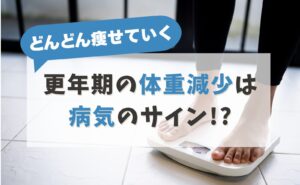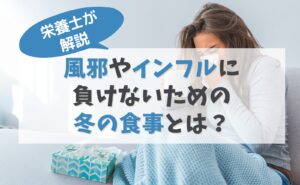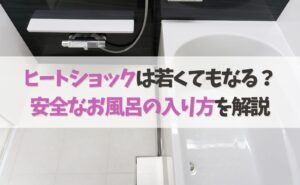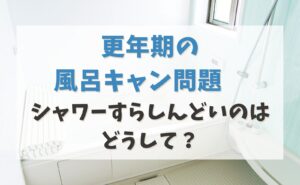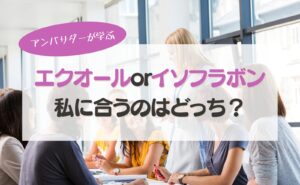閉経後の骨密度を上げる!食べ物や運動・生活習慣を解説

閉経後は骨密度が急激に低下する時期であり、骨粗しょう症リスクが高まります。骨密度が下がると、ちょっとした転倒でも骨折につながりやすくなり、生活の質が大きく低下するおそれがあります。
しかし、正しい生活習慣や知識を持つことで、骨を守ることは可能です。毎日の食事や運動などによって、骨密度の維持・向上を目指すことができます。
本記事では、閉経後の女性が骨密度を維持・向上させるためにできる具体的な対策を解説します。
50代女性は要注意!閉経後骨粗しょう症とは?
骨粗しょう症とは、骨の量や質が低下し、骨がもろくなって骨折しやすくなる病気です。なかでも、閉経を迎えた女性に多くみられるのが「閉経後骨粗しょう症」です。1
閉経後骨粗しょう症は、原発性骨粗しょう症に分類され、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少することによって引き起こされます。[1]2
エストロゲンは骨の代謝に深く関わっており、骨の形成と吸収のバランスを保つ働きがあります。閉経後はその調整機能が失われ、骨の吸収(壊す働き)が進みやすくなるのです。
骨がもろくなると、背骨の圧迫骨折や大腿骨骨折など、深刻な健康問題につながる可能性もあります。
閉経後に骨密度が下がる原因
女性の骨量は20代でピークを迎え、40代に入ると緩やかに減少し始めます。そして、閉経期に突入する50歳前後になると、エストロゲンの分泌が急激に低下し、骨の吸収が活発になるため、骨密度が著しく低下します。
他にも、骨密度低下の要因として以下のようなものが挙げられます。[1]3
- 運動不足
- カルシウム不足や偏った食事
- 無理なダイエット
- 喫煙
- アルコールの過剰摂取
- 日光に当たらない生活
特に、やせ型の女性や室内で過ごすことが多い人は、骨密度が下がりやすい傾向にあります。自分の生活を振り返り、リスク因子に当てはまっていないかチェックしてみましょう。
閉経後骨粗しょう症の症状
骨粗しょう症は「沈黙の病気」とも呼ばれ、自覚症状が出にくいのが特徴です。骨は徐々にもろくなっていくため、気づかないうちに進行しているケースも多く見られます。実際に骨折するまで気づかないケースも多く、健康診断などで指摘されて初めて知る人も少なくありません。
ひとつの目安として、20代の頃よりも身長が3cm以上低くなっている場合は、背骨の圧迫骨折が起きている可能性があります。背骨が潰れると姿勢が前かがみになりやすくなり、腰痛や背中の張りなどを感じることもあります。[1]
痛みなどの症状がなくても、骨密度の低下が進んでいるサインかもしれません。気になる場合は、早めに骨密度の測定を受けましょう。
閉経後の骨粗しょう症予防《生活習慣5つのポイント》
骨密度の低下を防ぐには、毎日の生活習慣の見直しが欠かせません。ここでは、閉経後の女性が意識したい5つのポイントをご紹介します。
1.カルシウムやビタミンD・ビタミンKを含む食べ物を摂取する
骨の材料となるカルシウムはもちろん、カルシウムの吸収や骨の形成を助けるビタミンD・Kの摂取も重要です。[2]4
| カルシウム | 牛乳・ヨーグルト・チーズ・小魚・小松菜・チンゲン菜・豆腐など |
| ビタミンD | サケ・サンマ・メカジキ・シイタケ・キクラゲ・卵など |
| ビタミンK | 納豆・ホウレン草・ブロッコリー・キャベツ・ニラなど |
1つの栄養素に偏らず、バランスよく摂取することが大切です。季節や好みなどで食べやすい食品を選びながら、継続できる形で取り入れましょう。
2.アルコールの過剰摂取や喫煙を控える
過剰な飲酒や喫煙は、骨の形成を妨げる要因です。[2]
タバコに含まれるニコチンは骨芽細胞の働きを抑え、エストロゲンの分泌も低下させます。アルコールもカルシウムの吸収を妨げるため、量を控えることが望ましいでしょう。
「1日1杯まで」など、自分なりのルールを設けると継続しやすくなります。
3.サプリメントを活用する
食事だけでは摂取が難しい場合は、サプリメントで補うのも選択肢のひとつです。
特にビタミンDは、食品だけでは十分な量を摂るのが難しく、閉経後は吸収率が下がることもあります。不足しやすい栄養素は、医師や薬剤師に相談してサプリメントを活用するなど上手に補いましょう。
4.無理のない運動で骨に刺激を与える
運動によって骨に適度な刺激を与えることで、骨形成が促進されます。[2][4]特に、以下のような運動がおすすめです。
- ウォーキング
- ジョギング
- ヨガ
- ピラティス
日常生活に取り入れやすく、全身の筋肉を動かす運動が理想です。テレビを見ながらのストレッチや、買い物ついでのウォーキングなど、「ながら運動」でも十分効果があります。
無理のない範囲で、楽しみながら取り組みましょう。
5.日光浴をする
日光を浴びることで、体内でビタミンDが生成されます。ビタミンDは骨密度の維持に欠かせない栄養素です。
- 冬場は30分〜1時間程度の外出
- 夏は木陰で30分程度(日傘や帽子を使ってもOK)
美容目的で紫外線を避けがちな人も、手や足だけでも日光に当てる習慣をつけるとよいでしょう。
定期的な骨密度測定で「骨の状態」を知る
骨粗しょう症は自覚症状が少ないため、早期発見には検査が重要です。特に以下のような人は、定期的な骨密度測定を受けることをおすすめします。
- 50歳以上の女性
- 身長が縮んできたと感じる(3cm以上縮んだら要注意)
- 運動習慣が少ない
- 家族に骨粗しょう症の既往がある
医療機関では、DEXA(デキサ)法という精度の高い検査が一般的に用いられています。腰椎や大腿骨といった骨折リスクの高い部位を対象に、骨の密度や強さを数値で評価できるため、リスクを客観的に把握するのに役立ちます。[1]
検査は数分で終わり、痛みもありません。市町村の特定健診の一環として受けられる場合もあるため、定期的な健康診断にあわせて検査の有無を確認しておくとよいでしょう。
とくに、これまで骨のケアを意識してこなかった方や、閉経前後のタイミングで体調の変化を感じている方は、現状を知る第一歩として骨密度検査の受診を検討してみてください。40代以降は、年に1回を目安に、健康診断とあわせて受けておくと安心です。
何歳からでも間に合う!閉経後骨粗しょう症予防
骨の健康は「もう遅い」とあきらめる必要はありません。閉経後でも、適切な対策を講じることで、骨密度の低下を食い止めたり、改善することができます。
エストロゲンの減少は自然な変化ですが、骨粗しょう症による骨折は予防が可能です。閉経期のホルモン変化と骨密度の低下は密接に関係しているため、できるだけ早めに対策を始めることが将来の骨折リスクを減らすことにつながります。
更年期は心身の変化が大きい時期ですが、生活習慣を見直すチャンスでもあります。骨折を防ぎ、いつまでもアクティブな人生を送るために、今日からできることから始めてみましょう。
毎日を元気に、自分らしく過ごすために、骨の健康にも目を向けていきたいですね。
出典