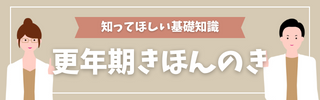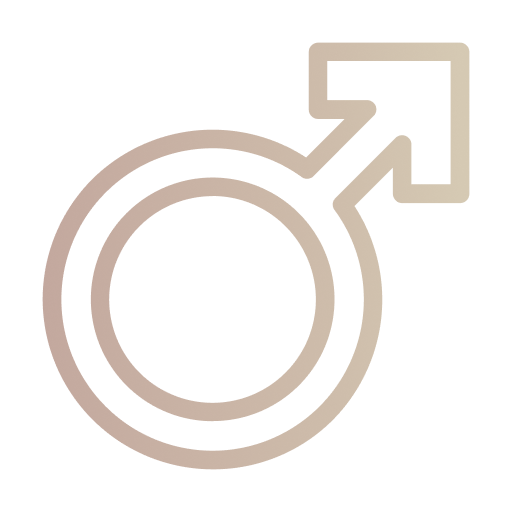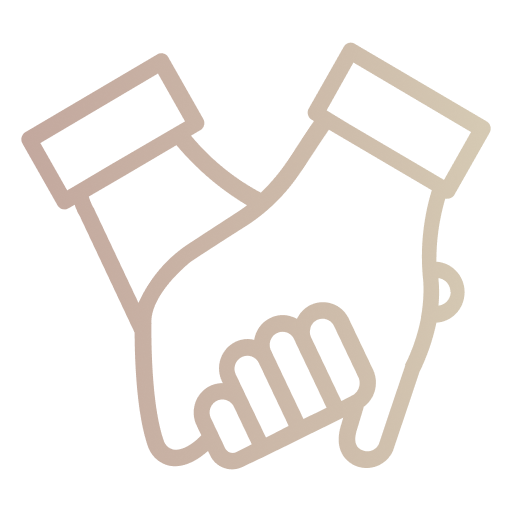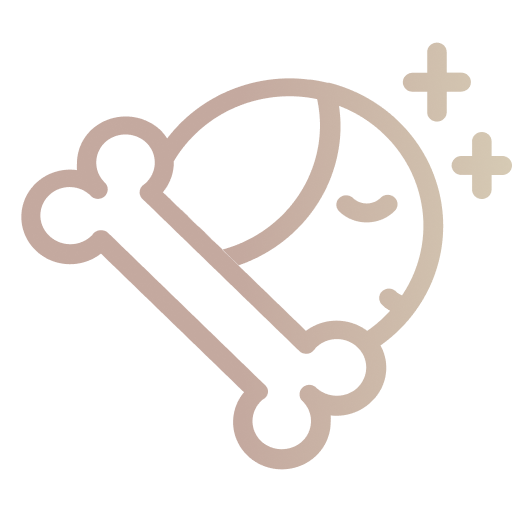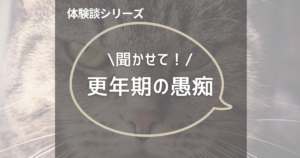女性医師に聞く、女性とうつ。ウィズコロナ時代を生きるために必要な対策とは?

男性よりも女性のほうが発症しやすいと言われているうつ病。ストレスや更年期など、原因はさまざまですが、特にコロナ禍では体の健康だけでなく、“心の健康”を維持することの難しさを感じている人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、これまでに多くの女性たちの悩みに寄り添ってきた家庭医療専門医の三島千明先生に、うつにならないための予防策や病院でどのような治療が行われているのか、などについて教えていただきました。


Q. 新型コロナウイルスが流行してから、うつ病を発症している女性は増えていますか?
診療現場での個人的な印象としては、うつの相談は増えているように感じています。いままでの環境が変わるだけでも非常にストレスのかかることなのに、これだけの短期間で生活習慣がガラッと変わってしまうことは誰も経験したことがなかったのではないでしょうか。
特に、最初の自粛生活が一回終わってまた元の生活に戻った方で、少し時間が経ってから徐々に、「思ったように能率が上がらない」「体がだるい」といった声が多く上がりました。新型コロナウイルスとの因果関係ははっきりしませんが、妊娠中や出産後の女性のうつが以前より増えていると報告されています。
Q.そんななかで、うつにならないための予防法というのはありますか?
まずうつ病や不安の改善に効果があると言われているのは、ウォーキングやヨガのようなあまり激しくない有酸素運動。運動することでストレスに効能がある「セロトニン」の分泌が促されます。セロトニンは「幸せホルモン」とも言われ、心の安定にとても大切です。自粛で家にこもりがちな生活において、体力の回復にも役立ちます。人込みを避けて感染対策をしながらであれば、散歩もよいと思います。自粛で家にこもりがちな生活において、体力の回復にも役立ちます。セロトニンは日光を浴びることでも分泌されますので、定期的に外で日光を浴びることも大切です。女性には、アロマテラピーなどのリラクゼーションもオススメですね。
あと、SNSやネットのニュースなど、不安をあおるような内容の情報から少し距離を置く、というのもこれからは必要かなと感じています。寝る直前までついずっとスマホを見てしまう方も多いと思いますが、スマホの光によって人を休眠や睡眠に誘う「メラトニン」というホルモンの分泌が下がり、睡眠のリズムが崩れてしまいます。難しいかもしれませんが、就寝の数時間ほど前から見ないようにしたり、時間を決めて使うようにすることがオススメです。
Q.ほかにもいまの特殊な状況下だからこそ、意識したほうがよいこともありますか?
まずは、生活のリズムを規則的にすること。家にいる時間が長くなるとどうしてもダラダラとしてしまいがちですが、毎日決まった時間に起きたり、食事を取るとか、お風呂に入るとか、当たり前のことをちゃんとするように心がけることは大事です。あとは、こんなふうに生活環境が大きく変わったときこそ、できるだけたくさんこまめに休息を取ることも実践してみてください。
それと、すべてをやろうと思わないことですね。真面目な方ほど、「なんで私はこんなこともできないんだろう」と自分を責めてしまったり、家事を完璧にこなそうとしたりしますが、「いまは普通ではない」ということをきちんと認識する必要があります。何でも100点を目指さずに、少し力を抜いてゆるく過ごしてみることですね。
Q.対人関係で心がけたほうがよいことがあれば、教えてください。
自分の気持ちを打ち明けられる場があることも重要なので、対面でもオンラインでも定期的に話す機会を持てるといいなと思います。というのも、自分の気持ちを抱え込み過ぎて、溜め込んでしまうのはよくないですから。うれしいとか、楽しいとか、つらいといった感情について話すのも大切なことだというのを覚えていてください。もし、悩んでいることがあれば、無理せずに周りにきちんと助けを求めるようにすることですね。
Q.それでもうつになってしまった場合、病院ではどのような治療法があるのでしょうか?
うつにも軽い状態から症状が重い場合によって異なりますが、抗うつ剤や不安に対する薬、漢方だったり、カウンセリングによる心理療法だったり、いろいろなアプローチがあります。一般的に、うつ病ではいろんなお薬を出されてしまうのではないかと怖いイメージを持っていらっしゃる人もいるようですが、最初からいきなり多くのお薬を出されるということはごく一部の場合と思います。
いまは「うつかな?」とご自身が思う症状に関しては、そのほかの身体の症状のチェックも含めて、最初は内科でも相談に乗ってくれることもあります。まずは、身近でかかりやすいところで相談していただくのもいいと思います。
Q.ちなみに、更年期うつにはどういった治療が効果的なのでしょうか?
更年期うつの方は、ホルモン補充療法や漢方、抗うつ剤、カウンセリングといった心理療法が一般的な治療です。実際はすべて行わなくても女性ホルモンを調整するだけで気持ちの面が改善される方もいらっしゃいます。
ただ、精神的な症状が強い場合は、精神科の医師を紹介する場合もあります。うつや不安に対する薬を処方することもあります。なので、その方に合わせた治療法を医師が見立てて一緒に選んでいくというのが一般的ですね。
Q.そのほかに女性が気を付けたほうがいいことはありますか?
基本的に女性は毎月生理の前後にホルモンのバランスの変化で、気持ちの落ち込みや精神的に不安定になりやすいです。最近は、「PMS(月経前症候群)」はかなり浸透してきていますが、PMSの中でも、特に心の不調が著しく、日常生活や社会生活に支障を来たしているような状態を「PMDD(月経前不快気分障害)」と呼びます。そういった症状が出やすい方は、毎月やってくる“波”とうまく付き合っていく必要があります。
適度な運動やリラクゼーションといったセルフケアが大切です。かかりつけ医に相談し、ピルや漢方を飲んでみたりするのもいいかもしれません。いろいろな対処法があるので、わからないことがあれば、何でも医師に相談していただくのがいいと思います。
Q.いま病院に行くのが怖いという人は、オンラインで診察を受けることもできますか?
そうですね、今回のコロナ禍で内科や心療内科、精神科を含めたさまざまな診療科でオンライン診療が広がり、オンラインのカウンセリングサービスも増えているようです。現在、医療機関では感染対策をしっかりと行って診療をしていますが、持病やリスクを抱える方、どうしても感染が心配という方もいらっしゃると思うので、オンライン診療も上手く利用していくことも、これからはより必要になってくるのかなと感じています。
Q.現在、うつの症状に悩まされている女性にアドバイスがあればお願いします。
私からお伝えしたいことは2つ。先ほども言ったように、いまのコロナ禍での生活はこれまでとは違う状態であり、これほどまでに人生観や社会様式が変わることは、私たちの人生ではありませんでした。それだけに、このこと自体がすごくストレスとなり、大きな負担が自分にかかっている状態なのだということをまずは認めてあげること。しっかりと受け入れて、ご自身が無理をしないことが大切です。適度に休憩しながら自分のペースで進んで行くことが大事なので、「怠けている自分を許さない」と思うのではなく、自分に優しく、がんばりすぎないようにセルフケアを心がけて欲しいです。
もうひとつは、普段からいろんなことを相談できるパートナーのようなかかりつけの医療機関を持つこと。病気になって、生活が立ち行かなくなってから病院を探すのではなく、予防や検診、ちょっとした体調不良でもいいので、定期的に行けるかかりつけ医を見つけて頂きたいなと思っています。そうすることで、何かあったときに対応も早いので、ぜひこれを機にみなさんにも考えて頂きたいです。
お話をうかがった先生

監修医師
三島千明 先生
島根大学医学部を卒業したのち、島根大学医学部付属病院で初期臨床研修を修了。
その後、北海道家庭医療学センターで、家庭医療後期研修を修了する。
現在は、青葉アーバンクリニックや丸の内の森レディースクリニックにて勤務。女性医師として、悩みを抱える女性たちが気軽に相談できるようなかかりつけ医を目指し、診療を心がけている。専門分野は、総合診療(家庭医療)、在宅医療。